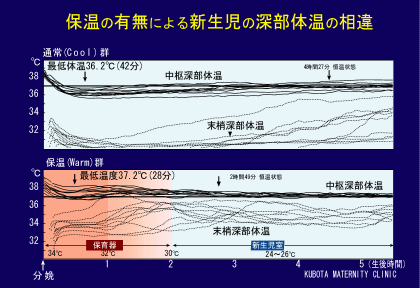 |
|
| (1) cool群(分娩室:24〜26℃)における体温変動の観察(上段) | |
| 中枢深部体温(直腸温)は生後42分で最低(平均36.2℃)となり約2.0℃の体温下降を認めました。その後体温は次第に上昇し、出生後平均4時間27分で恒温状態となりました。一方、足底部の末梢深部体温は出生直後より急激な体温下降を示し、生後1時間20分で最低(平均29.8℃)となり、以後中枢深部体温に連動し次第に上昇、平均6時間57分で恒温状態になることが判りました。出生直後の体温下降から恒温状態に至るまでの体温調節は、cool群では主に褐色脂肪組織の分解による化学的熱産生と、啼泣(crying)や体動などの筋肉運動による物理的熱産生に加えて、末梢深部体温の著しい下降、すなわち、末梢血管収縮による熱放散防止機構が体温保持に重要な役割を果たしていることが、中枢と末梢深部体温の同時観察によって明らかとなりました。 | |
| (2) warm群(保育器:34〜30℃)における体温変動の観察(下段) | |
| 中枢深部体温は生後28分で最低(平均37.2℃)となり、約1.0℃の体温下降が認められましたが、その回復はcool群より早く平均2時間49分で恒温状態(37.3±0.25℃)となりました。一方、末梢深部体温にはcool群にみられた著しい体温下降は認められず、また、中枢と末梢の深部体温差も少なく中枢深部体温に連動したリズミカルな体温変動がより早期から観察されました。このリズミカルな体温変動は、寒冷刺激に対する熱産生の増加や、熱刺激による発汗を伴わない環境状態を、つまり末梢血管の収縮と拡張によって体温調節が巧妙に制御されている状態(中性体温帯)を表現していると考えられました。 | |
| 以上の成績は、久保田らが医学誌Biology of the Neonate(1983)発表した内容の一部です。 |