| ■ 産湯(うぶゆ)と乳母(めのと) |
|
| むかしのお産は自宅分娩が主でした。また当時のお産では“産湯(うぶゆ)”を沸かしていました。昔の言い伝えに、冬に生まれる冬児よりも夏に生まれる夏児の方が育てやすいというのがあります。それは、赤ちゃんが生まれた時の気候、すなわち子宮内と産屋の温度差が、その後の赤ちゃんの発育に影響を与えたからではないか、と考えることができます。産湯の目的のひとつは、赤ちゃんの体を洗うと共に、お湯によって部屋の温度と湿度を上げ、また冷えた赤ちゃんの体を暖めるためであった可能性があります。現代のお産は施設分娩となり、常に25℃前後に空調された大人にとって快適な分娩室でのお産が行われています。この室温(約25℃)はお産をしている産婦さんや周囲の大人にとっては快適ですが、いままで37.5〜38℃の子宮内にいた赤ちゃんにとっては、この13℃の温度差は寒すぎることがわかったのです。赤ちゃんは、その寒さによる体表面からの熱の喪失を防ぐため、全身の末梢血管を長時間収縮させて、皮膚を青白くさせて身を縮めています。さらにその寒さは体表面の皮膚の血管の収縮を起こすだけではなく、消化管(腸)の血管まで収縮させ、哺乳障害(初期嘔吐)の原因となっていることもわかりました。すなわち、血管収縮によって腸の働きが抑制されているため、経口的に与えた(飲ませた)糖水や人工乳は数時間も胃の中に留まり(胃内停留時間=empting
time の延長)、時には赤ちゃんはそれらを吐いてしまうのです。さらに、生まれた直後の赤ちゃん(正常成熟児)を通常の分娩室の室温で管理すると、赤ちゃんのこの血管収縮が改善されるまでに6〜8時間くらいかかることもわかりました。この時期に発症する初期嘔吐は今まで生理的現象と考えられていましたが、当院では、赤ちゃんの環境温度の管理(生後2時間の保育器による保温:下図:保温群)でいっさい発症しなくなりました。またこの消化管の運動抑制は、胎便の排出時間を遅くし、重症黄疸や胎便による腸閉塞(胎便性イレウス)の原因となっていたこともわかりました。 |
| 保温によって哺乳障害を改善することは、出生後早期からの経口栄養を可能にし、発達障害の原因の一部である新生児早期の低血糖症や重症黄疸の予防につながります。生まれたばかりの赤ちゃんは、通常の室温管理では、手足を縮めて、皮膚も青白かったり紫がかったりして冷たく触れますが、当院の温度管理(下図:保温群)した保育器の中の赤ちゃんは、すぐに手足を伸ばし、皮膚もピンクで暖かく、目を開けて指しゃぶりをしたりしているのです。 |
|
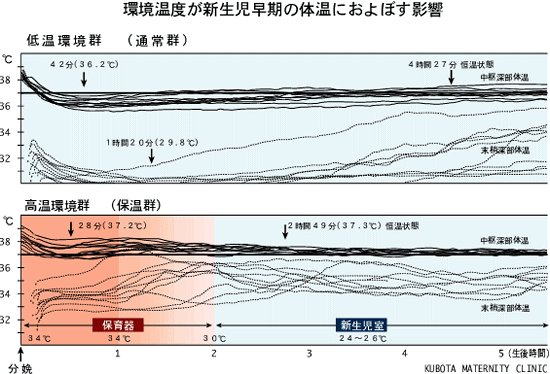 |
|
|
  |
|
|