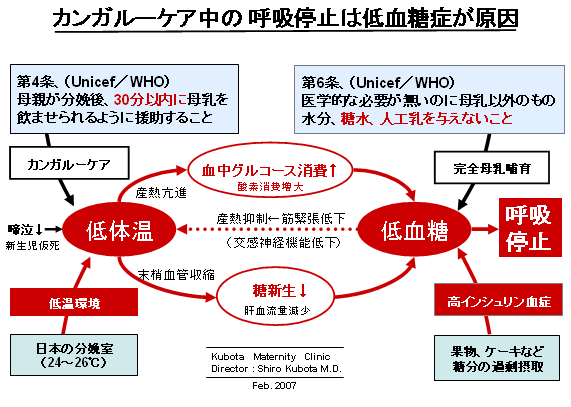| 第24回日本母乳哺育学会 (2009年9月27日・東京) ―抄録― |
|
| 日本の分娩室は新生児にとって“寒すぎる” | |
―出生直後の寒冷刺激の強さが、早期新生児の体温調節・糖代謝・ 消化管機能・ビリルビン代謝に及ぼす影響について― 医療法人 久保田産婦人科麻酔科医院 院長 久保田史郎 |
|
はじめに |
|
|
|
キーワード |
|
| 恒温動物、哺乳動物、早期新生児、低温環境、カンガルーケア、低体温症、自律神経機能、体温調節、低血糖、重症黄疸、頭蓋内出血、初期嘔吐、高インシュリン血症、 | |
1.日本の分娩室は寒すぎる |
|
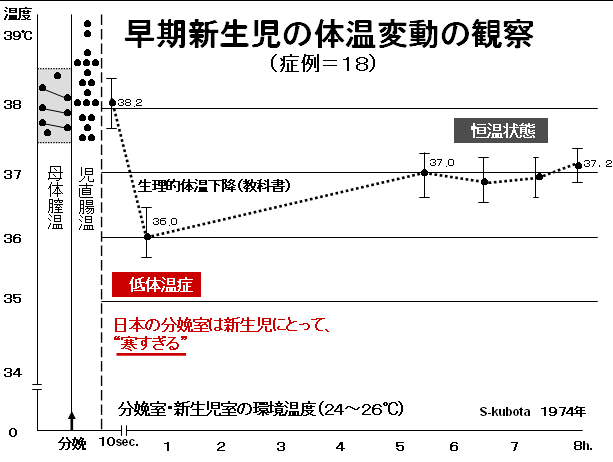 |
|
|
|
|
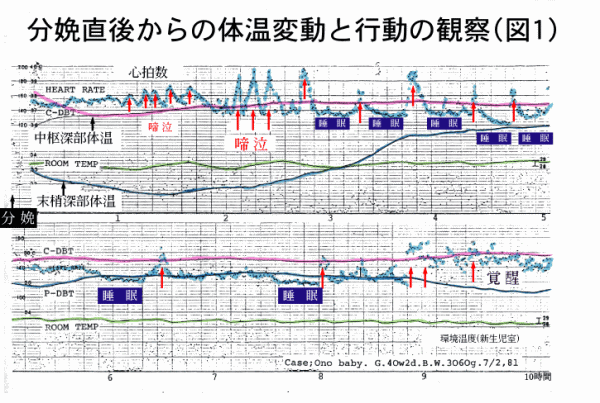 |
|
| 胎児は分娩を境に急激な環境温度の低下に遭遇し、生後1時間以内に約2.0℃~3.0℃の体温下降を余儀なくされる。胎内(38℃)と胎外(24~26℃)の環境温度差(約13℃)は出生直後の新生児にとって、“寒冷刺激”として呼吸を促進する上で重要な役割を果たしている。しかし、その寒冷刺激が強い場合、児は体温下降を防ぐために、放熱抑制(末梢血管収縮)と産熱亢進(啼泣=筋肉運動)という体温調節機構を作動させる。一般に、早期新生児は体温調節機能が未熟と考えられているが、新生児は出生直後から体温調節機構を巧妙に作動させ、低体温から恒温状態に移行する。出生直後の低体温の原因は、寒冷刺激による熱損失の方が産熱より優っているからである。 日本の分娩室(24~26℃)では、新生児は体温調節機構(放熱抑制+産熱亢進)の働きによって、生後5~8時間前後に恒温状態に移行するのが一般的である。しかし、児が何らかの理由によって「低体温⇔低血糖」の悪循環に陥った時、恒温動物である人間の体温調節機構、生命維持を司る自律神経機能に異常が発生する。 |
|
| ⒉ 体温調節機構に異常を招いた低血糖症の一例 |
|
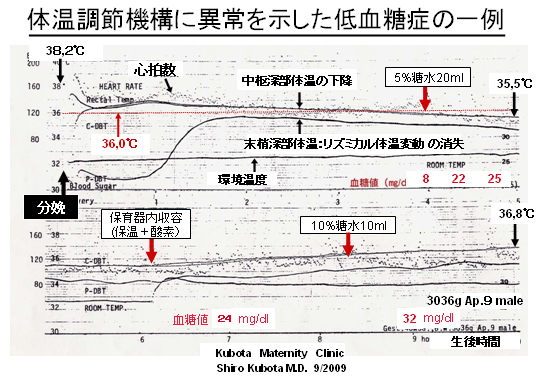 |
|
| 新生児の体温調節に関する研究を始めた時期(1981年)に、偶然にも遭遇した低血糖症の一例を紹介する。母親に妊娠糖尿病などの合併症はなく、児は3036g、正常満期産児、新生児仮死もない。分娩室・新生児室の室温は24~26℃であった。この症例の特徴は、生後2~6時間目に中枢/末梢の深部体温が並行して下降している事である。生後4時間目に中枢深部体温が36℃以下に下降したにもかかわらず、放熱抑制/産熱亢進のための体温調節機構が全く作動していない。心拍はサイレント(平坦)であり、啼泣(筋肉運動)もない静かな状態が記録された。この体温変動の特徴は、無脳児と同じ変温動物的なパターンを呈している事である。体温の異常に気づき血糖値を測定すると、重度の低血糖(8mg/dl)であった。速やかな治療、すなわち保育器内収容(①保温、②酸素投与、③糖水の経口摂取)により児は後遺症を残すことなく回復した。体温の測定中でなければ異常(低血糖症)に気付かず、脳に重篤な後遺症を残した可能性の高い症例である。当院が出生直後の体温管理(保温)と生後一時間目からの超早期混合栄養法にこだわる理由は、この低血糖症の一例に出会ったからである。 | |
3.カンガルーケアの問題点 |
|
1993年、厚生労働省がWHO/UNICEFの「母乳育児を成功させるための10か条」を後援した事によって、母乳推進運動は全国で積極的に展開されている。しかし、10か条の中で第4条(カンガルーケア)を日本の寒い分娩室で長時間にわたって行うと、新生児は「低体温⇔低血糖」の悪循環に陥る危険性が増す。
|
|
| ■ WHO/UNICEFの「母乳育児を成功させるための10か条」の問題点 第4条:母親が分娩後、30分以内に母乳を飲ませられるように援助すること |
|
| 分娩室の室温が出生直後の新生児にとって快適な環境温度(中性環境温度:30℃~32℃)に調整されていれば、第4条は何ら問題ない。しかし、カンガルーケアが始まった赤道直下のコロンビア(ボコタ)と違って、日本の分娩室は大人に快適(24℃~26℃)な環境温度に空調されている。胎内と胎外の温度差(約13℃)は出生直後の赤ちゃんにとって寒すぎるため、児は一過性の低体温症となる。その後、新生児は体温調節機構(放熱抑制+産熱亢進)を作動して、低体温から恒温状態に移行する。しかし、第4条(カンガルーケア)の管理法を間違えば、低体温は進み恒温状態への移行が遅れる。分娩直後からの低体温状態が続いた場合、生命の安全を司る自律神経は体温調節機構(放熱抑制+産熱亢進)を優先して作動させるため、生命維持装置(呼吸・循環・消化管・内分泌など)の機能に異常が発生する。生後30分以内のカンガルーケア中に、全身チアノーゼ・筋緊張低下・徐脈、ケイレン、呼吸停止などの危険な症状が発生すると報告がある。それらの原因は、出生直後の「低体温⇔低血糖」が体温調節機構・生命維持装置の安全を司る自律神経機能に異常を招いた結果と考えられる。 |
|
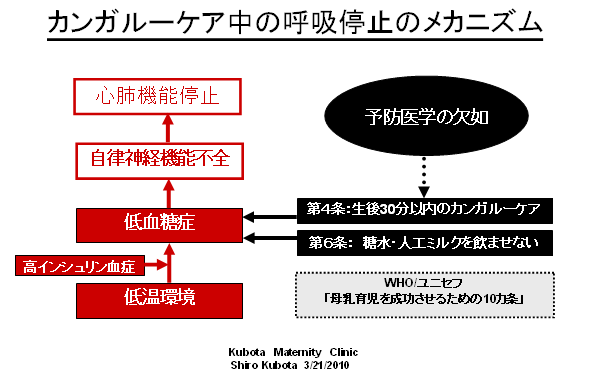 |
|
|
|
|
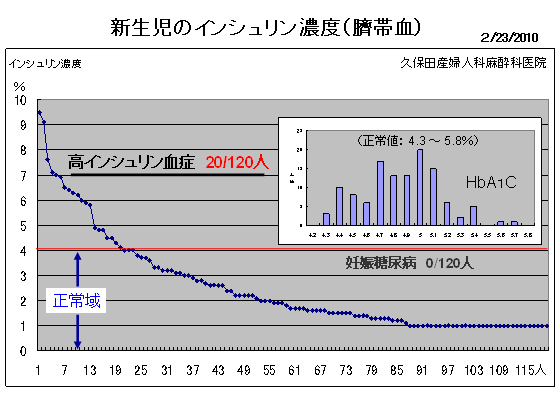 |
|
4.体温管理(保温)の目的 |
|
| 当院では生後2時間、赤ちゃんを保育器内(34→30℃)に収容する。その体温管理の目的は、(1)低体温を防ぎ、産熱亢進に要する無駄なカロリー消費を少なくし低血糖を防ぐ、(2)低体温予防によって、肝グリコーゲン分解による糖新生を促進し低血糖を防ぐ、(3)初期嘔吐をなくす事によって超早期経口栄養法を確立し、低血糖症・脱水・電解質の異常を防ぐ、(4)栄養不足の改善と胎便排出の促進によって重症黄疸を防ぐ、(5)低体温から恒温状態への移行を円滑にし、生命維持機構を司る自律神経の働きを正常化するためである。 | |
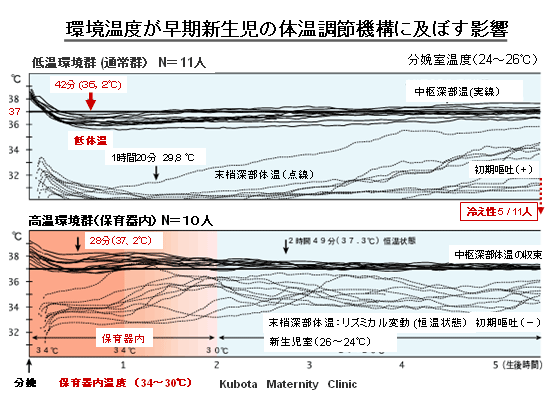 |
|
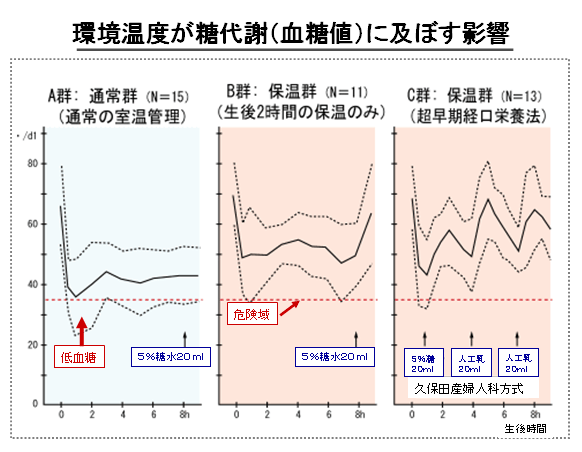 |
|
新生児管理 低血糖 |
|
| フローイーストクリニック 佐久間 泉 | |
| 新生児は酵素系やホルモン系の機能が未成熟で、容易に低血糖を起こし得る。病因はグルコース不足と高インスリン血症に大別される。従来、低血糖の診断にはCornblathの定義が用いられてきたが、最近は日齢や早産・出生体重の違いによらず40mg/dL以上を維持する管理が重要と考えられている。低出生体重児、母体DMなどリスクが高い場合はルチーンで血糖を測定し、低血糖(BS≦40mg/dL)の場合は直ちに輸液治療を開始して、糖の投与量が15mg/kg/分でも改善しなければ新生児持続性高インスリン性低血糖症などを鑑別してコルチコステロイド、グルカゴンなどを使用する。 (周産期医学 第40巻1号104頁)平成22年3月1日発行 日産婦医会報より |
|
5.新生児の重症黄疸は栄養不足が原因 |
|
新生児の重症黄疸は脳性麻痺・難聴の危険因子として知られる。その原因は生後数日間の栄養不足・胎便排出遅延が関与している事が分かった。一般に赤ちゃんは黄疸が出て当たり前と考えられている。しかし、出生直後の体温管理(保温)と母乳分泌に乏しい生後数日間の栄養不足を糖水・人工乳で補うことによって当院から重症黄疸が出なくなった。1983年の開業以来、当院で治療(光線療法)を要した重症黄疸の赤ちゃんは僅か25~30人(11,000人中)、総ビリルビン値20mg/dl以上は0人、新生児管理における予防医学の導入は重症黄疸のこれまでの医学的常識を覆した。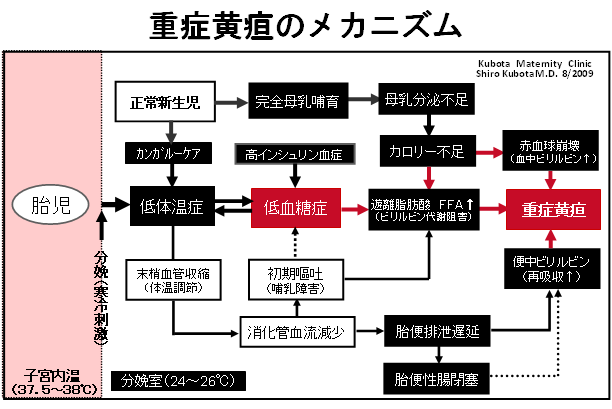 |
|
・重症黄疸の発生頻度 |
|
| 重症黄疸の発生率は施設間の保育管理法の違いで大きく異なる。光線療法の多い施設では30~40%前後、通常は10~20%前後、当院は0,5%以下。完全母乳の施設では摂取カロリー不足のため重症黄疸が強く出る。当院で光線療法が必要な重症黄疸がほとんど出ない理由は、基礎代謝量(50kcal/kg/日)に見合うカロリーを人工乳で補足しているからである。 | |
・重症黄疸を防ぐ目的 |
|
| ○重症(核)黄疸による脳性麻痺・難聴を防ぐ ○重症黄疸を防ぐ保育管理(保温+超早期混合栄養法)によって、発達障害の危険因子である低血糖症・頭蓋内出血を防ぐ ○重症黄疸の治療(光線療法)中の母児の隔離を防ぎ母児接触を保つ、光線治療のためのNICU入院を減らす ○低出生体重児(2000g~2500g)のNICU入院を減らし、NICU不足・たらい回しを防ぐ ○出生直後の低体温予防によって消化管血流量を正常化し、初期嘔吐・胎便性イレウスなどの消化管疾患の発生を未然に防ぐ |
|
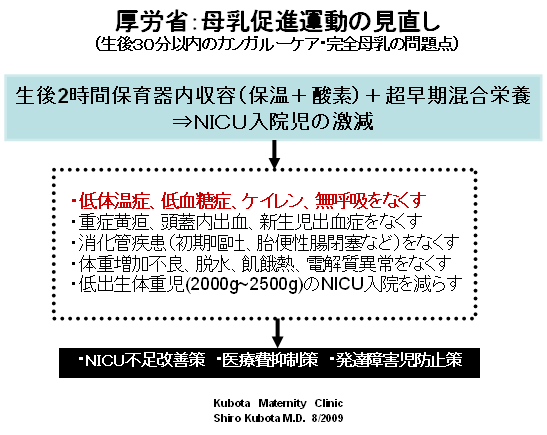 |
|
|
|
|
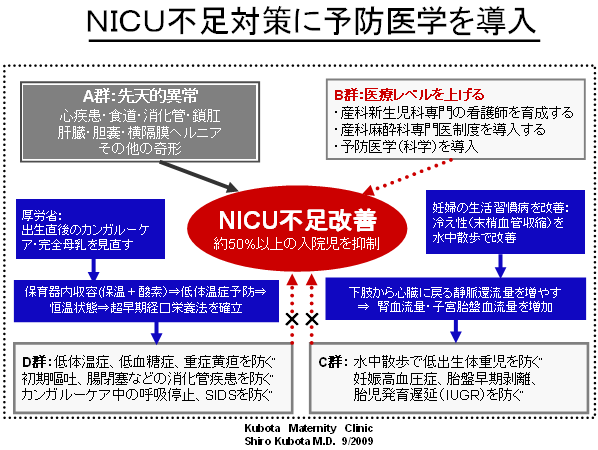 |
|
| ◎周産期医療に予防医学を導入すると、NICU不足改善、医療費・社会福祉費の削減効果が期待できる。重症黄疸・低血糖・頭蓋内出血・消化管疾患などの入院治療費だけで数千億円の削減が可能。NICU入院抑制効果、障害児発生防止などによる医療費・社会福祉費の削減効果は絶大である。厚労省は出生直後のカンガルーケア・完全母乳哺育を見直すべきである。 | |
結語: ■お産の歴史 |
|
| 1993年、厚労省がWHO/UNICEFの「母乳育児を成功させるための10カ条」を後援したのを契機に、出生直後の新生児管理は様変わりした。我国の歴史的な「産湯」の習慣は無くなり、生後30分以内のカンガルーケアが当たり前となった。出生直後のカンガルーケアと母乳が満足に出ない生後0~3日間の完全母乳栄養法は、低体温・低血糖・重症黄疸などの合併症を増やし児に不利益である事が分かった。 | |
■人間は恒温動物であり哺乳動物である。 |
|
| 現代の新生児管理の問題点は、哺乳動物である母乳促進運動を優先し、恒温動物である体温管理(保温)の重要性を忘れている事である。哺乳動物の消化管機能(吸啜・消化・吸収・排泄)は自律神経によって調節されている。その自律神経機能は低温環境下では体温の恒常性を保つための体温調節(放熱抑制⇒末梢血管収縮)を優先するため、消化管機能に悪影響(消化管血流↓⇒初期嘔吐)を及ぼす。母乳促進運動の第一歩は、いかに早く母乳を飲ませるかではなく、いかに低体温症を防ぎ、いかに早く恒温状態に移行させるかである。 本稿は、日本小児麻酔学会(福岡:2003年)、日本臨床体温研究会(札幌:2004年)、鹿児島県母性衛生学会(鹿児島:2008年)で教育講演したものをまとめたものである。 |