環境温度(寒冷刺激)が赤ちゃんの体温調節(放熱・産熱)に及ぼす影響
|
胎児は分娩を境に急激な環境温度の低下に遭遇し、生後1時間以内に約2.0℃〜3.0℃の体温下降を余儀なくされます。子宮内の温度は約37.5℃と一定で、生まれる前までは児が体温を積極的に調節する必要はありません。ところが、出生すると分娩室内の温度は24〜26℃と母体にとっては快適な室温ですが、子宮内の温度と比べると約13℃も低く、新生児にとっては寒い環境に直面し、出生直後から“寒冷刺激”が与えられることになります。この“寒冷刺激”は新生児の呼吸を促進する上で重要な役割を果たしますが、同時に新生児の体温を低下させることにもなります。
|
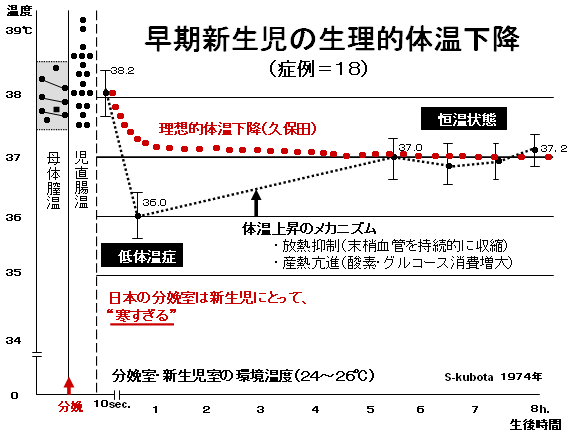
|
| 出生直後の赤ちゃんは、身を縮め、手足は冷たく、筋緊張を高め、産声を大きくあげます。これらの行動は、出生直後の体温低下を防ぐために行なわれています。身を縮めるのは放熱を防ぐためで、手足が冷たいのも末梢血管を収縮させて放熱を防ぐためです。筋緊張が強いのは全身の筋肉を収縮させることで熱産生を増やしているためです。産声はただ啼いているのではなく、胸やお腹の筋肉を大きく動かすことで熱を産生しているのです。このように放熱を抑制して産熱を亢進させる体温調節機構が出生直後から働いています。出生直後は環境温度の低下による熱損失の方が優って、新生児の体温は生後1時間以内をピークとして約2.0℃〜3.0℃程低下しますが、働き続ける体温調節機構(放熱抑制+産熱亢進)によって徐々に恒温状態に安定していきます。 |
|
|
しかし、日本の寒い分娩室で保温を怠り、生後30分以内にカンガルーケアを長い時間すると、赤ちゃんは低体温症(冷え性)に陥り、呼吸・循環・消化管などを司る自律神経機能に不具合が生じます。恒温動物である人間の自律神経機能は、呼吸・循環・消化管などの生命維持装置の働きを犠牲にし、体温の恒常性を保つ為の体温調節機構を優先して作動するからです。出生直後の低体温から恒温状態に安定するまでの熱産生には沢山のエネルギー(糖分)が消費されますので、栄養摂取が出来ていない新生児の低体温症には厳重な注意が必要です。出生直後の体温下降が強く、低体温(冷え性)から恒温状態への回復が遅れると、赤ちゃんは容易に低血糖症に陥ります。重度の低血糖症では、体温調節、生命維持機構を司る自律神経は機能不全に陥り、中等度の低血糖症でも脳の発達に永久的な障害を遺す危険性があります。早期新生児の管理で最も大事なことは、カンガルーケア・完全母乳をすることではなく、出生直後の低体温症を防ぎ、より早く恒温状態に安定させ、低血糖症を防ぐ管理をする事です。
|
   |