| 日本の分娩室は、赤ちゃんに寒過ぎる |
|
日本の分娩室(24〜26℃)は裸の赤ちゃんにとって快適かどうかを調べるために、低温と高温の二つの異なった環境温度を準備し、出生直後の低体温から恒温状態へ移行するまで体温変動の違いを観察しました。通常の分娩室(24〜26℃)で管理した11名をcool群(上段)、出生直後より生後2時間まで保育器内(34→30℃)に収容し、その後に新生児室(24〜26℃)に移した10名をwarm群(下段)としました。体温測定には電子深部体温計を用い、中枢深部体温(C-DBT)は前胸部で、末梢深部体温(P-DBT)は足底部で30秒毎に、同時に直腸温も測定しました。
分娩室の室温が出生直後の赤ちゃんの体温調節、糖代謝、消化管機能(初期嘔吐・胎便排出時間)にどんな影響を及ぼすのか、出生直後に低体温症となった赤ちゃんは、どの様なメカニズムで体温を回復し恒温状態に至るのか、両群の体温調節の特徴について解説します。
|
|
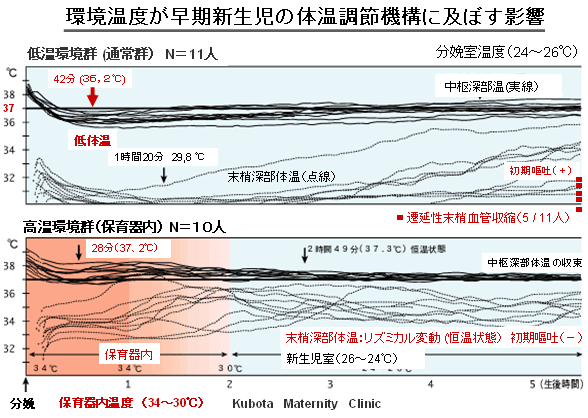 |
|
| ■cool群とwarm群における体温調節の違い: |
|
1. 中枢深部体温(C-DBT)の特徴
直腸温(C-DBT)は、cool群では生後約42分で最低(平均36.2℃)となり約2℃の体
温下降が、warm群では生後28分で最低(平均37.2℃)となり約1.0℃の体温下降が観
察された。生後2時間の体温管理(保温)の有無によって、両群の体温下降に約1.0℃
の違いが認められた。
2. 末梢深部体温(P-DBT)の特徴
興味深い点は、中枢深部体温(C-DBT)に連動した末梢深部体温(P-DBT)の体温変動です。cool群では出生直後よりP-DBTの急激な体温下降(最低:平均29.8℃)が全例に見られた。そのcool群の体温変動の特徴は、中枢と末梢の体温較差が大きいこと、生後5時間以上が経過したにもかかわらず体温の回復にバラツキがあり、約半数(5/11人)が32℃以下、つまり末梢血管が持続的に収縮した状態(冷え性)である事です。一方、warm群の特徴は、中枢と末梢の体温較差が少なく、出生直後からP-DBTにリズミカルな体温変動が全例に見られ、冷え性は一例も認められませんでした。つまり、warm群の新生児は、恒温状態への移行がより早く見られた事、冷え性の新生児が一人もいなかったことが特徴です。cool群では、約半数(5/11人)に冷え性(末梢血管収縮)の赤ちゃんが観察された事が、新生児の体温管理の上で注目すべき点です。
■環境温度が体温調節・消化管・肝機能に及ぼす影響
中枢と末梢の体温較差は産熱量を、末梢深部体温(P-DBT)の変動は末梢血管の収縮/拡張つまり放熱量を意味します。
1. cool群の体温調節のメカニズムは、放熱を防ぐための末梢血管収縮と熱産生を
増やすための筋緊張亢進(啼泣)によって、出生直後の低体温から恒温状態へと移行します。この際、体温下降の著しいcool群の新生児は、産熱量を増すためにwarm群より多くのエネルギー(ブドウ糖)と酸素を消費します。また放熱抑制を目的に末梢血管が持続的に収縮することは、足底部のみならず消化管の血流量を減少させ腸管の機能障害(初期嘔吐=哺乳障害)を招く要因となります。同時に、肝血流量も減少するために、肝グリコーゲン分解(糖新生)が抑制されます。即ち、早期新生児の低体温症(冷え性)は低血糖を促進する作用があることから、出生直後の体温管理(保温)は低体温症を予防するだけでなく、低血糖症を防ぐためにも重要な管理である事がわかりました。
2. 恒温状態(リズミカルな体温変動)に安定したwarm群の赤ちゃんは、生後間もなく吸啜反射が全例に見られ、初期嘔吐もなく、生後1時間目からの糖水の経口摂取が可能になりました。
■日本の分娩室は、赤ちゃんには寒過ぎる
warm群(保育器内収容)に見られるP-DBTのリズミカルな体温変動は、寒冷刺激に対する熱産生(カロリー消費)の増加や、熱刺激による発汗を伴わない、赤ちゃんにとって安全で快適な環境温度(中性環境温度)であることを証明しました。保育器内収容によって出生直後の低体温症を防ぎ、恒温状態への移行を早めることによって、早期新生児の呼吸・循環・消化管・内分泌系など全ての臓器の機能が正常に動き始めるのです。成書には早期新生児の初期嘔吐は生理的現象と書いてありますが、保育器内収容(保温)によって初期嘔吐の赤ちゃんは当院にはいなくなりました。初期嘔吐は生理的現象ではなく、出生直後の低体温症(冷え性=末梢血管収縮)が原因であることが分りました。 |
|
   |
|