| (4)完全母乳哺育が抱える問題点 |
|
| わが国は、赤ちゃんの死亡率が世界で最も少ない国になりました。しかし残念なことに発達障害児(脳性麻痺や視聴覚障害)の発生は減少していません。むしろ増加していると懸念する資料もあります。また、脳性麻痺の原因については1996年の米国での発表で、「脳性麻痺の発生時期は、1984年〜1985年では50%以上は分娩開始前であったが、1990年〜1992年には分娩前が発生時期と思われる脳性麻痺は大幅に減少し新生児期に発症した症例が増加した」、と報告されています。分娩中や新生児期以降などは変化していません(前掲の図:赤ちゃんの予防医学がなぜ必要か)。 |
| なぜ新生児期に発症する症例が増加したのでしょうか。わが国の実状はどうなのでしょうか。新生児期に原因があるものが増加したことに関して、完全母乳栄養推進運動による赤ちゃんの栄養不足との関連が気がかりです。WHO/UNICEFの母乳育児10カ条を、そのまますべての赤ちゃんに推進することには無理がある、と思えてならないからです。出産後のすべてのお母さんが分娩当日からひとり残らず十分な母乳分泌があれば問題はないのです。しかし、母乳分泌量は初産婦/経産婦で異なり、分娩後日数によっても異なります。最終的な母乳分泌量にも個人差があります。真正母乳分泌不全と診断される母乳のまったく出ないお母さん達もいます。分娩前後からしっかりと「おっぱいケア」をし母乳分泌促進を図っても、出産当日から2〜3日間はどうしても母乳分泌に乏しいのです。そのため、とくに初産婦や母乳分泌不足のお母さんから生まれた赤ちゃんは脱水や栄養不足となりやすく、その程度と日数によっては赤ちゃんが栄養失調状態となり、著しい体重減少はもちろんのこと、低血糖症/高ビリルビン血症(重症黄疸)/ビタミンK欠乏性出血症(脳出血)などを起こしやすくなるのです。 |
| わが国では周産期医療/新生児医療の進歩によって赤ちゃんの死亡率が大幅に減少しましたが、それは主に病気に対する診断と治療技術の向上によるものでした。これからのわが国の新生児医療は、正常新生児が異常にならないようにする、すなわち、正常に生まれた赤ちゃんが重症黄疸にならないようにする/低血糖症にならないようにする/新生児出血症にならないようにする、という「予防医学」を導入することが重要となると思います。最近増加傾向にあると懸念されている発達障害の原因の中には、新生児期の適切な管理によって予防できるものがあると考えられます。それらの予防可能な部分を、赤ちゃんの注意深いケアによって防止することは、われわれお産に携わるものの使命ではないでしょうか。「赤ちゃんはお母さんから3日分の水筒とお弁当をもって生まれてくる」だから、生後数日間は糖水や人工乳を補給しなくても良い、と言って完全母乳を推進してるグループがありますが、その説が真実ならば、なぜ完全母乳栄養児に重症黄疸の発症が多いのでしょうか。その説が本当に赤ちゃんにとって正しいかどうかは、科学的な根拠に基づいて決定されなければなりません。単に完全母乳哺育を推進しようとする目的のために根拠もなく昔の言い伝えを利用することは、被害者が反対意見を言えない弱者である赤ちゃんだからこそ、許されないのではないでしょうか。 |
|
| a.生理的体重減少について |
|
| 大人には栄養失調という病名がありますが、生まれたばかりの赤ちゃんに対しては体重が著しく減っても栄養失調という言葉を使うことはありません。多くの赤ちゃんは出生直後の体重と比べ、生後数日の間は体重が減少します。この早期新生児の体重減少のことを「生理的体重減少」と呼んでいます。小児科学の教科書には生理的な(正常な)体重減少の範囲は生下時体重の5〜7%以内であり、その体重減少の主な原因は、子宮の中の胎児は細胞外液の水分量が多く出産後の赤ちゃんはそれを失うためと記載されています。しかし、最近の完全母乳育児関連の学会や論文では、出産後の体重減少が10%までを正常とする意見が述べられています。時には、完全母乳の赤ちゃんの体重が15%まで減少したとも報告されています。果たしてその10%や15%の体重減少は正常と言えるのでしょうか。昔の教科書が間違っていたのでしょうか。 |
| 完全母乳を実行するとそのような異常な結果となるため、昔の教科書の正常値を無理に変更したり、都合の良い「古いことわざ」を利用してこじつけているようにしかみえません。体重減少率10%や15%が、赤ちゃんの栄養学的立場から正常であるという根拠があるのであれば、その根拠を示すべきでしょう。当院の哺育管理(超早期経口栄養法)では、赤ちゃんの体重減少率は下図に示したように5%未満であり、飢餓状態を反映すると考えられている血中遊離脂肪酸の濃度は、生後4時間目に最高値を示すだけで、以後8〜24時間後には臍帯血の値まで低下しています。当院のデータを基に、完全母乳の赤ちゃんの体重減少などを見ると、完全母乳の赤ちゃんの大幅な体重減少そのものが脱水/栄養失調であると思われます。 |
| またわが国の産科/新生児の一部施設が、完全母乳哺育の著しい体重減少を赤ちゃんの栄養失調(異常)ではなく(正常な)生理的体重減少として受け止めている背景には、それらの臨床医が哺育管理がまだ十分であったとは思えない1948年の米国で作成されたDancisの体重発育曲線を参考にして新生児の栄養管理を行っていること、もあるのではないかと思えるのです。 |
| WHO/UNICEFの母乳推進運動に厳正に従えば、母乳だけで果たして生後数日間に何カロリーの摂取が可能なのでしょうか。初産婦児などでは、生後3日間は基礎代謝量(50kcal/kg/日)の1/3から1/2以下のカロリーしか摂取できず、まさに栄養失調状態なのです。 |
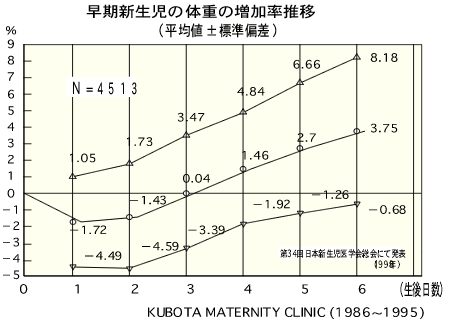 |
|
| b.新生児低血糖症について |
|
| 血液中のグルコース(血糖)は酸素と同じく脳の活動のために重要な物質です。そのためグルコースの異常な低下も脳に大きな障害を残します。妊娠中はお母さんの血液中のグルコースがすみやかに胎盤を通過し胎児へ移行するため、胎児が低血糖症になることはありません。分娩直後に臍帯(臍の緒)が切り離された後からは、赤ちゃんは自分でグルコースを産生し血液中の濃度が低下しないようにしなければなりません。生まれた直後の赤ちゃんの血糖値は徐々に低下し、通常では分娩後約1時間目ごろが最低値となります。多くの赤ちゃんの生後1時間目の血糖値は約40〜50mg/dl前後です。血糖値が異常に低下すると痙攣や無呼吸発作をおこすこともあります(症候性低血糖症)が、まったく症状がなく(無症候性低血糖症)血糖値が下がることも多いのです。血糖値の下降の程度と時間がどれくらい続けば脳に後遺症を残すかは不明ですが、最近の学会発表では、脳の保護のためにはこの最低値が40mg/dlより低くならないことが重要であるとされています。通常の赤ちゃんの管理では正常に生まれた赤ちゃんの血糖値を常時測定することはあまりしません。なぜなら「低体重出生児や糖尿病/肥満妊婦から生まれた赤ちゃんにはしばしば低血糖症が発症するが、正常満期産で生まれた赤ちゃんの血糖値が40mg/dlより下がることはほとんどない」と報告されているからです。しかし赤ちゃんの低血糖症は症状が乏しかったり(無症候性低血糖症)するため、発見や治療が遅れ脳に後遺症を残すことが稀ではありません。 |
|
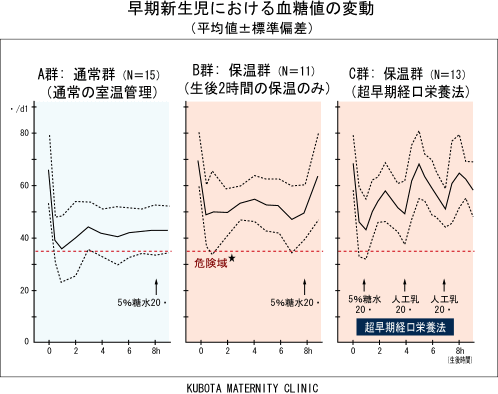 |
|
| 生後1時間目の血糖値はその赤ちゃんの糖産生能力などによって決まりますが、赤ちゃんに低酸素血症や低体温であれば、さらに不利になります。上図は出生直後からの赤ちゃんの血糖値の変化を、A) 通常の室温下での管理 B) 保育器のみによる管理 C) 保育器+超早期経口栄養法の管理で比較したものです。赤ちゃんの血糖値は通常での室温管理で最も大きく下降しその後の上昇も少なくなりました。しかし、保育器による保温のみでも血糖値の下降は改善され、しかも超早期経口栄養法では経口栄養の直後から血糖値が上昇しています。この結果から、保育器による保温が赤ちゃんの低血糖の予防に、ある程度有効であることが解ります。超早期経口栄養法で糖水やミルクを飲んだ直後からすぐに血糖値が上昇しているのは、保温によって末梢血管が拡張し、消化管の血行が改善されて腸の消化/吸収機能が良くなったためです。通常温度による管理では、たとえ早期から経口栄養を始めても、消化管の機能が悪く血糖値はすぐには上昇しません。 |
| 下図は新生児の体温研究を始めた時期にたまたま遭遇した「無症候性低血糖症」の一例です。母親に糖尿病などの合併症もなく妊娠40週3日で生まれた3036gの正常満期産児でした。分娩中や分娩直後の低酸素血症もなく通常の室温で管理していました。下図にはその赤ちゃんの体温変化と血糖値を示しています。図中の中枢深部体温/末梢深部体温についての説明はこのHPの「SIDS:メディカル朝日原稿」に解説があります。この体温図の特長は、中枢深部体温と末梢深部体温が並行して下降していることです。このような体温変化は中枢神経系を欠いた無脳児に見られます。おかしいと気づき血糖値を測定すると8mg/dlと極めて高度の低血糖症でした。その後の処置により「症候性低血糖症」となることも後遺症を残すこともなく回復しましたが、偶然に体温を測定中でなければそのまま放置され、中枢神経系の後遺症を残した可能性もあるのです。新生児低血糖症は後述のビタミンK欠乏症と同じく、発症してしまえば脳に重篤な後遺症を残す可能性が高く、予防が最も重要なのです。 |
|
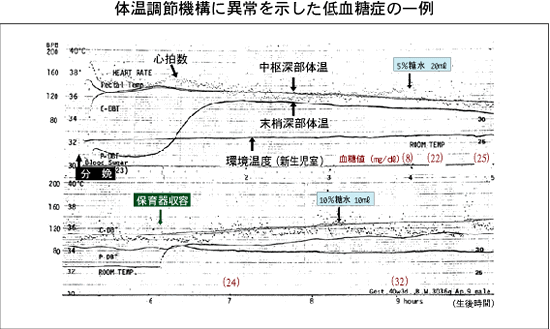 |
|
| わが国のある学会発表では、完全母乳栄養を目指す産科病棟における低血糖(血糖値40mg/dl以下)の赤ちゃんの発生率は、2000〜2500gの低出生体重児で約20%で、37週以降の満期産児でも9%に認められたと報告されています。そのため赤ちゃんの血糖検査を頻繁にする必要があると論じられ、とくに完全母乳栄養における低血糖症の発症に対して注意が促されています。そのようないつ発症するかも知れない低血糖症に対して、発症してから治療を開始した方が望ましいのか、それとも治療をしなくてすむように「予防医学」を優先させ、発症を未然に防ぐ方が望ましいのか、結論は明らかではないでしょうか。われわれ哺乳動物にとって母乳の素晴らしさは誰もが認めるところです。しかし、母乳の長所に気を取られる余り、短所を見失うことになってはならないと思うのです。 |
|
| c.重症黄疸について |
|
| 出生後4〜6日して赤ちゃんが黄色くなるのは、赤血球が壊れできたビリルビンが皮膚に沈着したものです(黄疸)。このビリルビンは脂肪と結合しやすいため、脂肪の多い脳の細胞に結合しその機能を障害します。もし、ビリルビン値が高い状態(高ビリルビン血症=重症黄疸)が続けば多くの脳細胞が障害され、脳性麻痺となります。赤ちゃんの重症黄疸は古くて新しい問題です。過去10数年前までは脳性麻痺の原因といえば重症黄疸(核黄疸)でした。その当時は黄疸の原因と治療をめぐっての研究が大きく進展し、その結果、重症黄疸の予防と早期治療が可能となり、核黄疸による脳性麻痺は大幅に減少したのです。しかし黄疸による脳性麻痺は、近年ふたたび注目を集めています。わが国のある資料(昭和58年から平成6年まで)によれば、産婦人科関連の医療事故の頻度は他の診療科に比べて圧倒的に多く全体の32%を占めています。その中でも重症黄疸による脳性麻痺の発生頻度は相変わらず多く、新生児管理事故の第一位(26%)を占めているのです。最近では脳性麻痺ばかりではなく聴力障害(難聴)の原因のひとつにも高ビリルビン血症が指摘されています。 |
| 赤ちゃんの赤血球の破壊の原因として血液型不適合妊娠が重要ですが、血液型不適合がなくても赤ちゃんの赤血球(ヘモグロビンF)は壊され大人の赤血球(ヘモグロビンA)に置き換えられます。その際ビリルビンが血液の中へ出てくるのです。その時もし赤ちゃんに栄養不足があると高ビリルビン血症が発症しやすくなることが知られています。すなわち栄養不足(饑餓)状態では、1)ヘモグロビンの分解酵素の働きが強くなりビリルビン産生が増加する、2)血中の遊離脂肪酸が高値となり肝臓でのビリルビンの無毒化(抱合)を障害する、3)食事摂取量の減少のため腸の蠕動運動が低下し胎便(ビリルビンを多く含んだ胎児の便)排泄が遅れビリルビンが再吸収される、などのため黄疸が重症化しやすいと報告されています。黄疸の研究と予防/治療法の進歩によって、交換輸血が必要な高度な重症黄疸は減少しましたが、光線療法を必要とする中程度の重症黄疸の発生頻度はそれほど減少していません。また、そのような中程度の黄疸の発症率は各地の産科施設によってバラツキがあり、完全母乳哺育に取り組んでいる産科施設では、とくに光線療法を受けた赤ちゃんが多いと報告されています。しかも、完全母乳哺育をさらに普及させようと活動しているグループの一部からは、多少の重症黄疸の発生の増加は完全母乳哺育のためには止むを得ない/母乳性黄疸だから心配はない、と受け止めている発表もあります。当院の母乳性黄疸に関する調査では、1ヶ月健診時における赤ちゃんの血中ビリルビン値は、完全母乳の赤ちゃん(906例)の平均は3.7mg/dlで、人工乳のみの赤ちゃん(239例)の平均は1.7mg/dlで、母乳栄養による差はわずか2mg/dlでした。 |
|
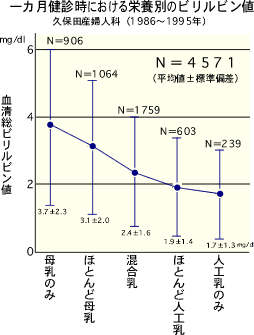 |
| わが国の1年間の出生数は約120万人ですが、その内の10〜15%(12〜18万人)前後の赤ちゃんが重症黄疸(高ビリルビン血症)の治療を行っているものと推察されています。たとえ高ビリルビン血症となったとしても、適切な光線療法などの治療を受ければ核黄疸(脳性麻痺)にはならないはずなのですが、それにもかかわらず重症黄疸による脳性麻痺や聴覚障害(難聴)が発生しているのです。もし、生まれた直後の赤ちゃんの適切な体温管理(保温)と栄養管理(超早期経口栄養)によって重症黄疸(高ビリルビン血症)そのものが発生しなくなるとしたらどうでしょう。またその体温と栄養の管理が、赤ちゃんをその他の様々な合併症から守り、かつ医療費の大幅な削減につながるとしたらどうでしょう。当院の体温管理(保温)と栄養管理(超早期経口栄養)では、生後4日目の赤ちゃんの血中総ビリルビン値の平均は7.2±2.0mg/dl(1998年)5.7±1.8mg/dl(2000年)と低値で、光線療法などの治療を必要とする重症黄疸は、この10年間の約5,000例で一例も発症していません。一方、完全母乳栄養群(新生児学会誌)の発表では赤ちゃんの血中総ビリルビン値の平均は12.8±3.6mg/dlと高値です。 |
|
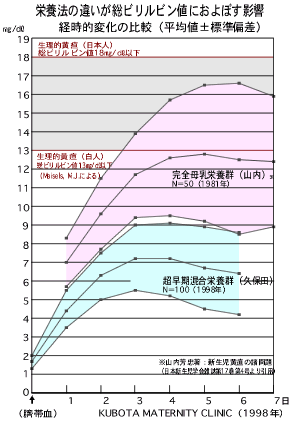 |
| 今までのわが国の報告では、われわれ東洋人と白人の赤ちゃんの黄疸の出方を比較するとわれわれの赤ちゃんの方が黄疸が強く、その主な原因は人種差にあると考えられてきました。例えば、わが国での血中総ビリルビン値(黄疸)の正常上限は18mg/dlであり、米国での上限は13mg/dlでした。しかし、当院の哺育法では赤ちゃんの血中総ビリルビン値が10mg/dlを超えることはなくなったのです。黄疸の原因は今まで考えられていたような人種差などではなく、単に栄養不足が原因だったのです。そのため多くの教科書の黄疸に関する診断や治療法の基準なども早急に見直される必要があると思われます。 |
| 最近では、その米国でも赤ちゃんの重症黄疸が注目を浴びています。赤ちゃんのビリルビン値は生後4〜6日目に最高値となりますが、米国では出生後2〜3日にはすでに退院しているため、赤ちゃんの重症黄疸の診断と治療に問題が生じてきたと報告されたのです。その理由は米国でも母乳栄養が増加してきたためです。メディカル朝日(1996)によれば「ミシガン州では退院した赤ちゃんの再入院が増えていて、その再入院には母乳栄養と黄疸/脱水が最も大きく関与していた」と報告されています。この報告では再入院し黄疸の治療を受けた赤ちゃんの血中ビリルビン値の平均は19mg/dlでした。よって、母乳栄養の赤ちゃんは退院後も脱水(栄養不足)や重症黄疸に対する注意が必要である、と警告されたのです。 |
| いままでのわが国では、赤ちゃんの黄疸は生理的現象として当たり前のように受け止められています。当院の超早期経口栄養法が明らかにしたように、胎児赤血球は赤ちゃんの栄養不足で壊れやすくなり肝臓での処理も悪くなるのです。すなわち、赤ちゃんの黄疸の強さは赤ちゃんの栄養の状態の良し悪しを反映しているのです。栄養状態の悪い赤ちゃんでは、体や脳の発育のみならず前述の低血糖症やビタミンK欠乏性出血症も心配です。これまでのように、ある程度の黄疸は生理的現象だから異常なしと放置するのか、それとも危険信号(イエローカード)として受け止め栄養不足を補い黄疸が出ないようにするかは、赤ちゃんんのその後の発育に大きな影響を与えることになるのです。 |
|
| d.ビタミンK欠乏症新生児出血症について |
|
| 出血は血液が固まる(凝固する)ことによって止まります。血液が凝固する力が弱まると、小さなきっかけで出血が起こり、赤ちゃんでは消化管出血(血性嘔吐や血便=新生児メレナ)や脳出血の原因となります。ほとんどの凝固因子は肝臓で生成されますが、凝固因子の第2、第7、第9、第10因子の生成にはビタミンKが必要です。すなわち、ビタミンKが欠乏すると赤ちゃんに血液凝固障害を引き起こし、新生児出血症を招く危険性があるのです。ビタミンK欠乏性頭蓋内出血(脳出血)の頻度は約1/2,000人ですが、いったん発症すると予後不良な(生命の危険や後遺症の可能性が高い)ので、予防が重要です。よってわが国では、厚生労働省が推奨して、正常成熟児にも出生直後・産科退院時・一ヶ月健診時のビタミンK2シロップの予防的経口投与を行っています。 |
| 「新生児のビタミンK欠乏性出血症は未熟児に多く、成熟児では生後2〜4日目に多く発症する」というのがこれまでの常識でした。しかし、ある政令指定都市の31施設の3年間(1993-95)で発症したビタミンK欠乏性出血症についての報告によれば、新生児出血症80例中21例(26%)は出生当日(第0日目)、34例(43%)は出生第1日目でした。すなわち発症した赤ちゃんの約70%が、生後48時間以内の早期発症でした。出血部位は消化管出血が86.5%と最も多いのですが、頭蓋内出血も8.9%に達しています。その報告で特記すべきことは「頭蓋内出血のほとんどが出生初日の発症で、その全例が厚生労働省が推奨している出生直後のビタミンK2シロップの投与を受けていなかった」と述べていることです。また、「発症した赤ちゃんは、予想に反して未熟児/低出生体重児が少なかったこと、さらに80例中50例(63%)は正常妊娠/正常分娩であったこと」が特徴でした。なぜ早期発症例が増えたのでしょうか。なぜ正常成熟児に多く発症したのでしょうか。なぜ出生直後にビタミンK2の予防投与を受けなかったのでしょうか。完全母乳栄養をめざすグループの一部には、赤ちゃんに一度でも糖水や人工乳を飲ませるとその後の母乳の飲みが悪くなると発言している人々がいます。その発言を信じて完全母乳栄養のためにビタミンK2シロップの予防投与の時期を遅らせたり中止したのあれば、重大です。赤ちゃんは周囲の哺育の方針に対して反対はできないのです。母乳哺育は重要なことですが、赤ちゃんへの危険性を軽視してまでも、死守しなければならないものなのでしょうか。当院の超早期経口栄養法では、出生直後から数日間は母乳以外の他の栄養(糖水や人工乳)を補給しますが、それ以降はお母さんの母乳哺育を奨めています。ただし母乳分泌が不足するお母さんには不足分を人工乳で補うように指導しています。ビタミンK2シロップは生後1時間目に投与しています。その結果、当院で生まれた赤ちゃんには、生後1ヵ月以内の消化管出血や頭蓋内出血は一例も発症していません。母乳中のビタミンKの含有量は初乳が最高値で、以降は低下し続けます。母乳育児の場合、ビタミンK欠乏による赤ちゃんの頭蓋内出血は生後2〜3ヵ月目にも起こることがあります。母乳中のビタミンKが不足していることに加え、母乳栄養児の腸内細菌にビフィズス菌が多くビタミンKを産生しないためです。人工栄養児ではビタミンK欠乏症にはなりません。ミルクにビタミンKが含まれていることに加え、腸内細菌に大腸菌が多く大腸菌はビタミンKを産生し赤ちゃんがそれを吸収するためです。そのため当院では、母乳栄養のお母さま方には、納豆などのビタミンKを多く含む食事を奨めたり、時々は赤ちゃんにビタミンKを多く含むミルクを飲ませるように指導しています。その理由は当院で生まれた赤ちゃんのうちただ1人ですが生後3ヶ月目に突然の脳内出血でなくなっていたからです。その赤ちゃんは当院の完全母乳群(906名)の1人でした。 |
|
| e.新生児くる病について |
|
| 米国では、この10年間でビタミンD欠乏症(くる病)の赤ちゃんが増加し(メデイカル・トリビューン2000年10月号)、ビタミンD欠乏症を発症した赤ちゃんに発育不良/骨折/O脚などを生じているとのことです。また「原因は母乳栄養にあり母乳中のビタミンDの含有量が少ないことである」と断言しています。そのためノースカロライナ州では母乳栄養の全乳児にビタミンD/A/Cを含む薬液の配布を開始したとのことです。 |
| くる病の予防にはカルシウム/ビタミンD/日光が必要です。日本では母乳栄養でくる病が増加したという発表はありません。わが国と米国との食生活や風習の違いなどが影響しているのかも知れませんが、わが国でも食生活などが欧米化している今日では、赤ちゃんのビタミンD欠乏症に注意しておくことも重要と思われます。 |
|
|
   |
|