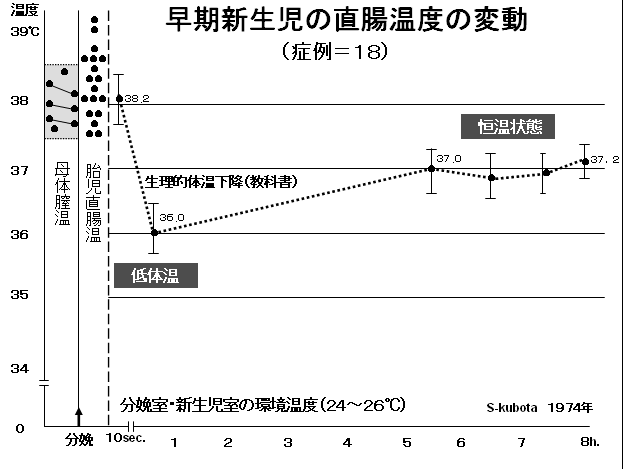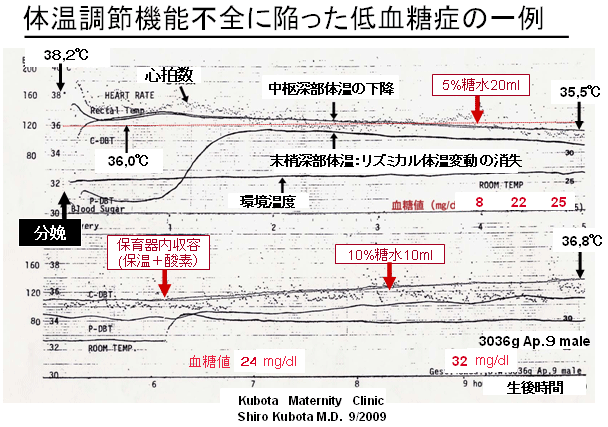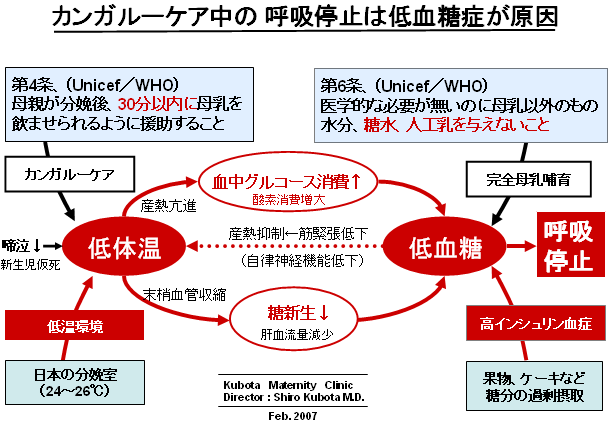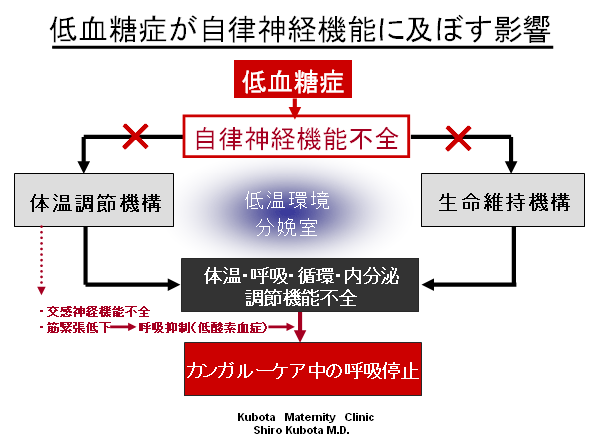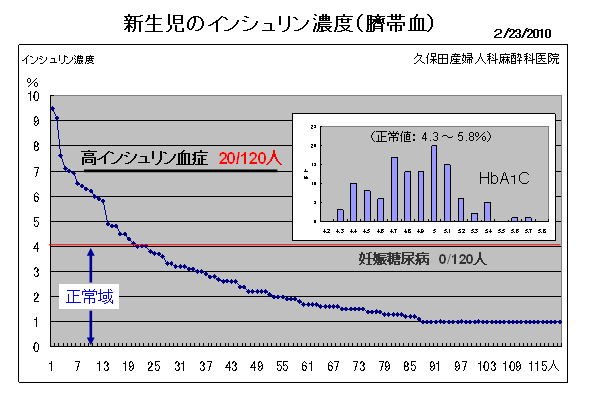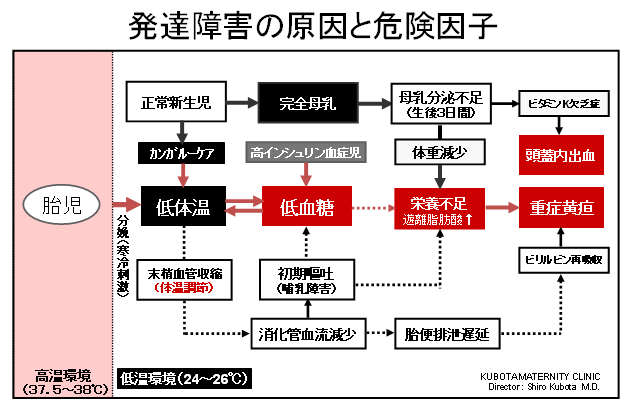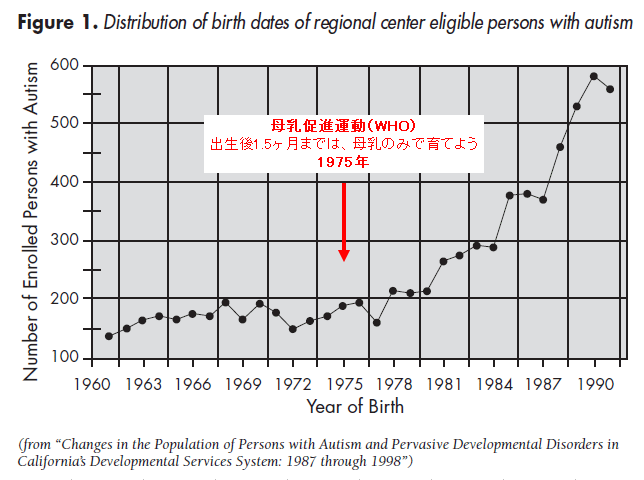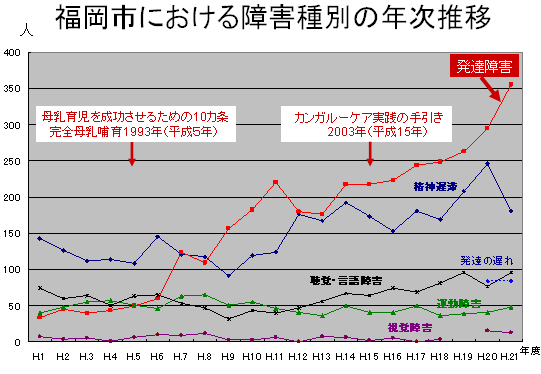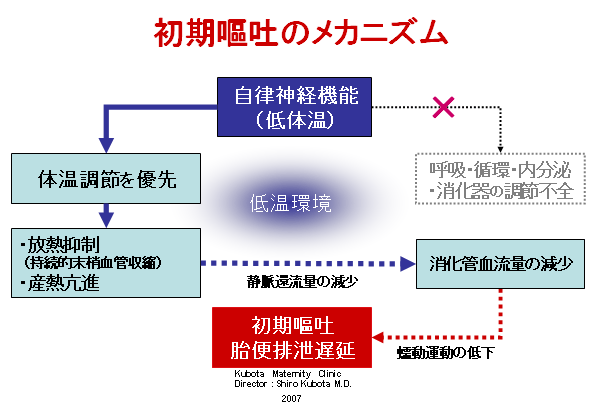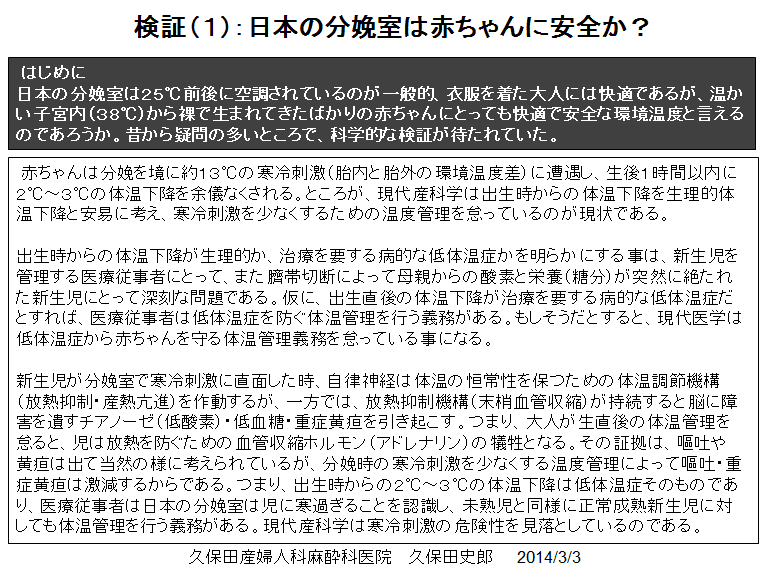 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
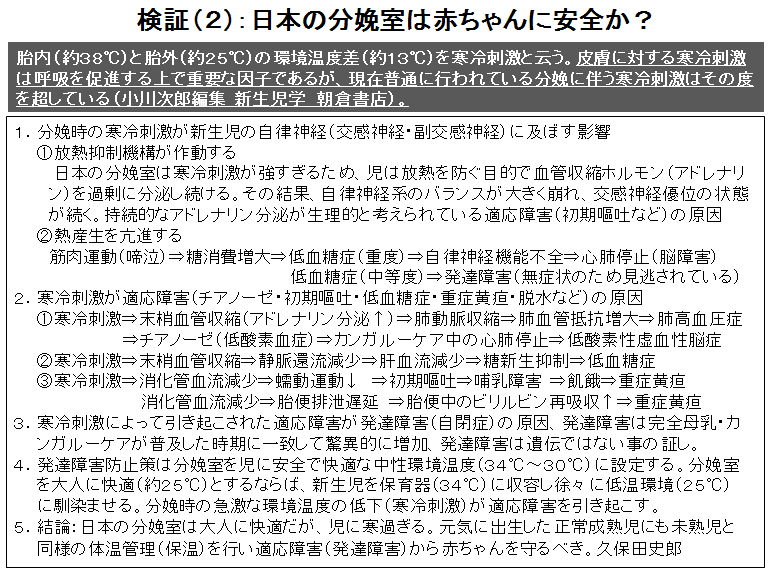 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本のお産は安全ではない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第49回 日本母性衛生学会総会(教育講演)2008年11月 国立成育医療センター周産期診療部産科医長 久保隆彦 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いつから「日本のお産は安全」という神話が流布されたのか? お産の現場で毎日働く多くの周産期医療従事者にとって予測できない突然起こる分娩時大量出血、母児救急を経験する度に「お産は怖い」ことを実感する。しかし、妊婦は脳天気なマタニティー雑誌や宗教にも近い自然分娩回帰カリスマ達によって分娩の持つ怖さはオブラートに包まれ快適なお産のみかのように洗脳されている。こういったことが間違った認識を生み出しているのだろう。 確かに、日本の母体死亡は戦後急速に減少し、世界最高のレベルとなった。この快挙の理由は、分娩場所が自宅・助産所から診療所・病院に移行したことと、日本特有のコンビニ産科(開業医産科医と看護師による全国のどこでもアクセスが良いお産形態)と一次施設に起こった母児救急に対して速やかに搬送可能な二次・三次施設の余裕に他ならない。だが、その素晴らしいシステムが危機に陥っている。「看護師内診問題」で多数の一次診療所が分娩から撤退した。「福島県立大野病院事件」で産科のマンパワーが減少した。この2つのことにより、一次・二次分娩施設は姿を消し、周産期医療体制ピラミッドは崩壊し、三次施設に分娩は集中し、本来三次施設が担わなければならないハイリスク妊娠・分娩あるいは母児救急受け入れが困難となった。 しかし、今日本は奇妙な方向に向かおうとしている。産科医が減少すれば助産師の権限を強化し、助産所で分娩を行えばよいという政策である。戦後のあの高い妊産婦死亡率、暗黒の周産期医療成績の象徴であった助産所分娩に戻ることは狂気といえる。まだ10年前なら助産所からの緊急母児搬送を三次施設が受け入れたので、考えられるオプションだったが、当センターでも助産所からだということで優先的な搬送受け入れはできず、これは全国の基幹周産期センター同様である。 さらに、日本産婦人科医会が行なった助産所から母体・新生児搬送された母児の予後は悲惨なものであった。医療が不可能な施設での分娩は危険といわざるを得ない。しかも、世界で最も安全に助産所分娩を行っているオランダでのリファー率(助産所でリスクを見つけ病院に紹介する率)は50~70%と高率であるが、わが国の助産所からのリファー率はわずか7%に過ぎず、日本の助産所での妊婦のリスク認知率・発見率は低いといわざるを得ない。演者が日本産婦人科学会で行なった全国調査で、わが国のいかなる妊婦でも250人に1人は分娩で死にいたるアクシデントに遭遇し、その半数は大量出血によるものだった。迅速な輸血ができない場所での分娩を本当に妊婦が望むのであろうか。今国民は真剣にお産について考えなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カンガルーケア(早期母子接触)中の心肺停止事故を検証する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ―心肺停止は不快(寒い・暑い)な環境温度が原因、病気ではなく事故である― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はじめに 出生直後のカンガルーケア(早期母子接触)と完全母乳哺育・母子同室が組み合わさって、新生児が低酸素性虚血性脳症に陥る事故が多発しているが、その原因を乳幼児突然死症候群(SIDS)と決め付けて処理しようとするのが現在の状況である。しかし、カンガルーケア等による事故をSIDSとして決め付ける事は、その発症メカニズムが全く異なることから、直ちに見直すべきである。以下に詳述する。 1. 自律神経の仕組み 「自律神経系」は循環、呼吸、消化、発汗・体温調節、内分泌機能、生殖機能、および代謝のような不随意な機能を制御する働きを持つとされる (wikipediaなどでもそうした認識が一般的)。ところが、人間が震えや汗をかくような不快(寒い・暑い)な環境温度に遭遇した時、自律神経は呼吸器・循環器・消化管などの制御より、体温の恒常性を保つための体温調節機構(放熱+産熱)を優先して作動する。しかし、自律神経に体温調節機構を優先して作動するという「優先順位」の概念は現代医学に無い。そのために寒い分娩室で生まれた赤ちゃんの呼吸・循環・消化管・肝臓などの内臓諸臓器の機能は、寒さから身を守るための体温調節機構(放熱・産熱)の犠牲になる。例えば、生後間もない赤ちゃんの呼吸循環動態は不安定と厚労省は決め付けているが、不安定になる理由は、寒い分娩室で低体温症を防ぐための放熱抑制機構つまり末梢血管を収縮させるためのホルモン(アドレナリン)が持続的に分泌し、肺血管を攣縮(肺高血圧症)するからである。内臓諸臓器に対して自律神経が本来の機能を作動させるためには、人間が快適な環境温度にいる時、体温が恒温状態に安定している時、低血糖症・低酸素血症に陥っていない時にのみ制御可能となる。生命維持の安全が確保される為には、体温が恒温状態に安定している事が絶対条件である。それは人間が恒温動物であるからである。 2. 自律神経は環境温度に支配される 自律神経は交感神経系と副交感神経系の2つの神経系で構成されている。呼吸循環などの腹部諸臓器の機能を正常に作動させるためには、快適な環境温度下で交感神経・副交感神経のバランスを平衡に保ち、体温を恒温状態に安定させることが新生児管理の基本である。赤ちゃんは恒温状態に安定し、低酸素・低血糖症に陥っていなければ、心肺停止が突然に起こることはない。環境温度(寒い・暑い)によって交感神経・副交感神経のバランスが大きく崩れ、その状態が長時間に及んだ時に呼吸循環・消化管・肝臓などの諸臓器にトラブルが発生する。例えば、寒い分娩室で体温管理・栄養管理を怠った時のトラブルが、冷え症・チアノーゼ・初期嘔吐・低血糖・黄疸などである。しかし、産科学教科書では、それらの殆どを生理的現象と考えている為に、医学が進んだ今も、脳に障害を遺す低血糖症・重症黄疸を防ごうとする発想はない。何故ならば、医者・助産師・看護師は、それらの適応障害を病気ではなく生理的現象と刷り込まれているからである。赤ちゃんにチアノーゼ・黄疸などの危険な症状が出ても驚かないのはその為である。 ★ カンガルーケア中の心肺停止は、病気ではなく医療事故(大阪事例) 分娩を境に急激な環境温度の低下に遭遇した赤ちゃんの体温を、いかに早く恒温状態に安定させるかを考える事が赤ちゃんを心肺停止(適応障害)から守るのである。出生直後の寒い分娩室でのカンガルーケアは自律神経のバランスが崩れ交感神経優位となり、この状態が長引くと呼吸循環動態・消化管機能・糖代謝に害を及ぼす。従って、寒い部屋でのカンガルーケア(早期母子接触)は、生命維持の安全を司る自律神経の機能を無視した危険極まりない医療行為であると断じる。寒い部屋で自律神経がまだ不安定な赤ちゃんを窒息の危険性が高いうつ伏せ寝にして寝かせ、さらに赤ちゃんの全身状態が何も観察できないようにタオル・毛布などで全身を覆い、母親一人に児の全身管理を任せるカンガルーケア中の心肺停止事故は、起こるべくして起きたと考えるべきで、事故責任は間違いなく医療側にあり、母親には何ら責任はない。 3.環境温度(寒い/暑い)が自律神経に及ぼす影響 3-①:低温環境が自律神経に及ぼす影響 低温環境下では、自律神経は放熱抑制と産熱亢進の二つの体温調節機構を優先して作動する。放熱抑制には末梢血管収縮(アドレナリン分泌↑)、産熱亢進には筋緊張亢進(筋肉運動=啼泣↑)を強制的に働かせる。ところが、放熱抑制機構(末梢血管収縮)は体温調節には有利に働くが、持続的なアドレナリン(血管収縮ホルモン)の分泌亢進は呼吸循環・消化管・肝臓などの腹部諸臓器に血流障害を引き起こす。また産熱亢進(筋肉運動=啼泣)が長時間に及ぶと、熱産生にエネルギー(糖分)がより多く消費されるため、母乳分泌が少ない時期に糖水・人工ミルクを全く飲ませなければ容易に低血糖症に陥る。新生児が重度の低血糖症に陥れば、無脳児の赤ちゃんと同様に体温調節・呼吸循環の調節ができなくなり心肺停止に至る。中等度の低血糖症が持続すると脳に障害を遺す。発達障害は原因不明とされているが、福岡市の調査によれば発達障害は完全母乳(1993年)・カンガルーケア(2007年)が普及した時期に一致して驚異的に増えていることから、発達障害は遺伝的要因を考える前に、まず、出生時の低血糖症・重症黄疸の関与を疑うべきである。つまり、発達障害児を防ぐには、出生直後の体温管理(温めるケア)と栄養管理(低血糖予防)を最優先すべきである。 ★ カンガルーケア(早期母子接触)は、 「冷え症」の赤ちゃんを増やす! 出生直後のカンガルーケア(早期母子接触)の長所には、体温上昇作用・血糖値・呼吸循環の安定があると報告されているが、日本の分娩室において体温上昇作用を検証したデータはない。あるのは、体温上昇作用が無い事を示唆する論文だけである。カンガルーケアに体温上昇作用がなければ、血糖値・呼吸循環の安定もあり得ない。日本の寒い分娩室(24℃~26℃)では、出生直後のカンガルーケアに保育器と同様の体温上昇作用は無いため新生児は低体温を防ぐ目的で末梢血管を持続的に収縮する。持続的な末梢血管の収縮は全身を循環する温かい血流量の減少を来すため、とくに手足を冷たくする。それが冷え性(末梢血管収縮)である。カンガルーケア中の心肺停止の事例は、顔色は蒼白・紫色、そして手足が冷たい「冷え症」が特徴であるが、SIDSの赤ちゃんは汗を出し顔色は良く(ピンク)、高温状態(うつ熱)で発見されることが殆どである。両者には末梢血管収縮(冷たい)と末梢血管拡張(温かい)の正反対の違いがある。この違いこそが、低温環境と高温環境に遭遇した時の恒温動物である赤ちゃんの生理的反応である。 ★ 冷え性は、「低血糖症」の赤ちゃんを増やす! カンガルーケアが「低血糖症」を促進する理由は、肝臓を循環する血流量が減少するからである。肝血流減少によって肝グリコーゲンの分解(糖新生)が抑制され、さらに産熱亢進によって血中グルコースの消費量が増えるからである。つまり、低温環境下で完全母乳の赤ちゃんに長時間のカンガルーケアを行うと低血糖症は進み、脳に永久的な障害を遺すリスクが高まる。低血糖症の危険因子はカンガルーケア・完全母乳だけではない。出生前に診断がつかない高インスリン血症児を寒い分娩室でカンガルーケアを行うと、低血糖症は避けられない。高インスリン血症児を低血糖から守る為にも、カンガルーケアを推進する医師・助産師は、高インスリン血症児は妊娠糖尿病の母親からだけでなく正常妊婦からも高頻度に生まれている事実を知り、低血糖症に対する予防策を講じるべきである。尚、高インスリン血症児の危険性については、2009年9月 日本母乳哺育学会(東京)で、「日本の分娩室は新生児にとって寒すぎる」と題して報告した。 3-②:高温環境が自律神経に及ぼす影響 汗が出るような高温環境下では、自律神経は放熱促進と産熱抑制の二つの体温調節機構を強制的に作動する。放熱促進には末梢血管拡張(アドレナリン分泌↓)、産熱抑制には筋緊張低下(筋弛緩)によって体温上昇を防ぐ。放熱促進だけで体温の恒常性が維持できなければ、熱産生を減らすために赤ちゃんは筋肉を弛緩させ眠りに入る。ところが衣服や布団の着せ過ぎによって衣服内温度が上昇し続け、睡眠中の赤ちゃんに寒冷刺激が加わらなければ睡眠からの覚醒は遅延し末梢血管は拡張したままとなる(覚醒反応遅延)。長時間の末梢血管拡張(アドレナリン分泌抑制)は不整脈(QT間隔延長)を、筋弛緩は呼吸運動を抑制し、赤ちゃんを低酸素血症に陥らせる。不整脈・低酸素血症が長時間に及ぶと心肺停止の危険性が高まる。また乳幼児をうつ伏せ寝で寝かせると腹部からの放熱が妨げられ、代償的に末梢からの放熱を増やすために末梢血管拡張(アドレナリン↓)を余儀なくされる。うつ伏せ寝でアドレナリン分泌抑制が持続すると窒息の危険性が増すだけでなく、不整脈・低酸素血症はさらに強くなる。それがSIDSの正体である。 4.赤ちゃんに事故が多い理由 赤ちゃんを心肺停止・発達障害から守るために、医療従事者は快適な環境温度を準備し、低血糖症・低酸素血症を防ぐための栄養管理・呼吸管理を厳重に行う義務がある。赤ちゃんに事故が多い理由は、大人と違って自力で不快(寒い・暑い)な環境温度から逃げ出すことが出来ないからである。また赤ちゃんを管理する医療従事者が体温管理・栄養管理の重要性を分かっていないからである。 5.結論 カンガルーケア中の心肺停止事故・SIDSは原因不明の病気と考えられているが、真実は病気ではなく事故である可能性が高い。不快な環境温度(寒い・暑い)に対する人間の体温調節機構(交感神経優位/副交感神経優位)が呼吸循環器などの生命維持機構に害を及ぼしたことによって誘発された事故(医原性疾患)と考えている。低温環境下における体温調節機構つまり放熱抑制を目的とした末梢血管収縮(アドレナリン↑)と産熱亢進(筋肉運動⇒糖消費増大⇒低血糖)がカンガルーケア中の心肺停止・発達障害の大きな要因であり、逆に、着せ過ぎなどによる高温環境における体温調節機構つまり放熱促進を目的とした末梢血管拡張(アドレナリン↓⇒不整脈⇒低酸素血症))と産熱抑制(筋弛緩⇒呼吸運動抑制⇒低酸素血症))がSIDSの要因となる。つまり、カンガルーケア中の心肺停止(交感神経優位)と、SIDS(副交感神経優位)は正反対のメカニズムで発生する。したがって治療法も異なる。 そう考えると、産科医療補償制度の原因分析委員会が「カンガルーケア中の心肺停止」を「SIDSの疑い」と診断していることには大きな矛盾がある。両者の心肺停止の原因が見つからない理由は、それらは病気ではなく不快な環境温度が引き起こした事故なのに、事故という観点からの原因解明がなされてこなかったからではないか。また原因分析委員会のメンバー構成(産婦人科医4人・小児科医1人・助産師1人・弁護士2人)にも問題がある。産科医療補償制度は産科医療の質の向上を目的とするとあるが、カンガルーケア中の心肺停止の原因解明を本気でやるのであれば、上記メンバーの他に、呼吸循環/臨床体温/臨床生理が専門である麻酔科専門医数人を委員会に加え、公平に検討すべきである。現行の産婦人科医・小児科医・助産師は周産期医療の専門家ではあるが、赤ちゃんの呼吸循環/臨床体温/臨床生理が分かる専門家ではない。麻酔科専門医が検討委員会にいたならば、カンガルーケア中の心肺停止事故をSIDSの疑いと誤って診断する事はない。 日本SIDS学会は乳幼児突然死症候群を原因不明の病気と定義しているが、SIDSは病気ではなく事故であるという視点から原因究明にアプローチすべきである。そして何より急がれるのが、厚労省と日本周産期新生児学会は、「授乳と離乳の支援ガイド」を見直し、母乳育児の3点セット(カンガルーケア・完全母乳・母子同室)の推奨を即刻中止することである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成26年1月26日 久保田産婦人科麻酔科医院 院長 久保田史郎 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当院の温めるケアと超早期混合栄養法の必要について動画で紹介 保育器で恒温状態に落ち着いた赤ちゃん 乳幼児突然死症候群(SDIS)から赤ちゃんを守るために 1.乳幼児突然死症候群(SIDS)の原因と予防法その1 2.乳幼児突然死症候群(SIDS)の原因と予防法その2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カンガルーケア(早期母子接触) は、百害あって一利なし ―赤ちゃん “冷え症”に注意― |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.赤ちゃん、元気ですか! 元気な赤ちゃんとは、顔色が良く、食欲(吸綴反射)があり、便が出て、体重が増え、栄養と水をきちんと摂っている赤ちゃんの事を指す。ところが、厚労省の母乳育児の3点セット(カンガルーケア+完全母乳+母子同室)を忠実に実践すると、赤ちゃんは吐き気のため食欲はなく、飲んでも直ぐに吐いてしまい、胎便排泄も遅い。仮に、食欲があったとしても母乳が全く出ていない為に、人工ミルクを補足しなければ容易に飢餓状態(脱水+低栄養)に陥る。近年、出生時からの体重が10%以上も減少し、脱水に陥り、治療(光線療法)を要する重症黄疸の赤ちゃんが目立つが、その理由は出生直後のカンガルーケアで冷え症(末梢血管収縮)の赤ちゃんが増えた事、さらに糖水・人工ミルクを飲ませない完全母乳哺育が普及した事による。つまり、厚労省が推奨する出生直後のカンガルーケアと完全母乳は、元気に生まれた赤ちゃんを不健康に育てる保育法と言わざるを得ない。福岡市の発達障害児は完全母乳哺育が普及した1993年頃から増え始め、2007年のカンガルーケア導入後から脅威的な勢いで増加している。完全母乳とカンガルーケアの短所が赤ちゃんを不健康(発達障害)にしている可能性が強い。 2.産湯と乳母の役割 昔は、赤ちゃんを元気に育てるために「産湯」に入れ冷え症を防ぎ、乳母を雇い出生直後から母乳を満足に飲ませることによって飢餓(脱水+低栄養)を防いでいた。しかし、厚労省は産湯・乳母に代表される予防医学の重要性を無視し、危険度の高い非科学的なカンガルーケアと完全母乳哺育を強引に取り入れたのである。厚労省は授乳と離乳の支援ガイドを作成し完全母乳とカンガルーケアを推奨したが、産婦人科専門医の反対を押し切って、なぜ助産師一人の非科学的な意見を聞き入れ、検証もせず、「授乳と離乳の支援ガイド」を慌てて公表したのか、疑問だらけである。厚労省の授乳と離乳の支援ガイドの見直しがない限り、発達障害児の増加に歯止めが掛からない。赤ちゃんの安全性を無視し、カンガルーケア・完全母乳を推奨した厚労省の責任は重い。助産師は自然を重要視するが、自然には科学(予防医学)がない。科学がない所で、医療事故が多発していることを厚労省が知らない筈がない。カンガルーケア中の心肺停止事故は完全母乳哺育を重要視する「赤ちゃんに優しい病院」に多いことが分かっているのである。 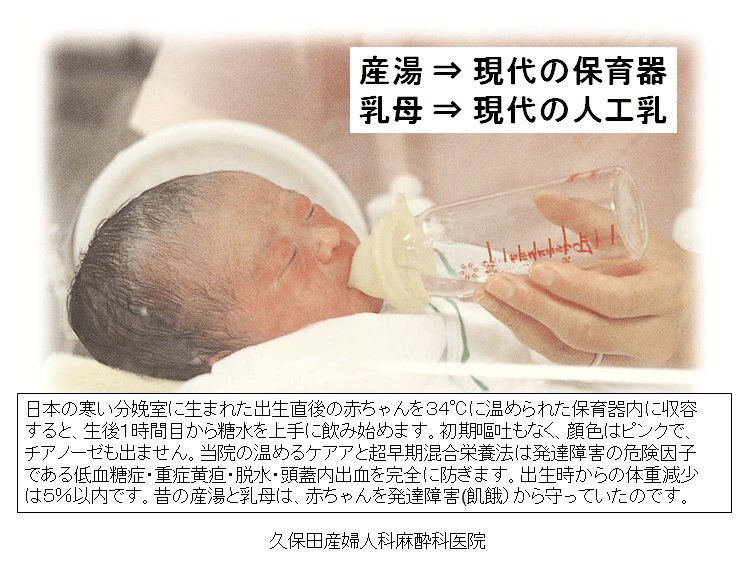 3.赤ちゃんの冷え症に注意! 約38℃の温かいお腹の中から25℃前後の寒い分娩室に生まれてきた赤ちゃんは、体温を37℃に維持するために末梢血管を持続的に収縮させ、放熱を防ぐための体温調節機構を作動させる。この時、赤ちゃんの手足は冷たく、所謂 冷え症の状態である。冷え性、つまり末梢血管が持続的に収縮すると下肢から心臓に戻る静脈還流量が減少し、血圧が低下する。冷え性は消化管血流量を減少するため腸の蠕動運動を抑制するが、その結果、赤ちゃんは食欲を無くし、胎便排泄を遅らせる。冷え症は消化管機能(消化・吸収・排泄)に害を与えるだけでなく、全ての臓器に障害を与えるため出生直後の冷え症対策には濃厚な医学的管理(保温)が必要である。分娩を境とした胎内から胎外生活への適応障害のほとんどは、冷え性(末梢血管収縮)が原因である。冷え性は万病の元といわれるが、赤ちゃんの冷え症は大人以上に深刻である。何故ならば、冷え性(末梢血管収縮)は肺高血圧症(チアノーゼ)を誘発し、赤ちゃんを低酸素血症に陥らせ心肺停止の原因となるからである。さらに肝臓における肝グリコーゲン分解による糖新生を抑制するため低血糖症に陥らせ、発達障害の危険性を増すからである。発達障害はカンガルーケアの普及後から驚異的な早さで増えていることから、冷え症(末梢血管収縮)による肺高血圧症(低酸素血症)・低血糖症・重症黄疸を防ぐ為の医学的管理が最重要である。カンガルーケアと完全母乳を推進する厚労省と日本周産期新生児学会は、発達障害児を防ぐための対策を早急に講じるべきである。 4.出生直後のカンガルーケア(早期母子接触)に、体温上昇作用なし! 新生児の冷え症の原因は、分娩室・母子同室の室温が寒過ぎるにもかかわらず、体温管理(保温)を怠っているからである。昔は赤ちゃんを産湯に入れ体温管理(保温)をしていたが、カンガルーケアが導入されてから産湯には入れないようになった。カンガルーケア(早期母子接触)には体温上昇作用があると日本周産期・新生児学会誌に報告されているが、その体温上昇作用を科学的に検証した研究はどこにも無い。カンガルーケアは温めるケアではなく、冷え症の原因となる「冷やすケア」なのである。日本の寒い分娩室(25℃前後)で体温管理を怠り、出生直後からカンガルーケアを長時間行うと、初期嘔吐・胎便排泄遅延(便秘)の赤ちゃんが増える。胎便排泄が遅延すると黄疸が強く出るが、便中に含まれるビリルビン(黄疸の基)が腸管内から血中に再吸収され血中ビリルビン濃度が上昇するからである。 5.カンガルーケア(早期母子接触)は、百害あって一利なし! 出生直後の赤ちゃんを保育器に2時間収容し冷え症を防ぐと、出生直後から食欲もあり、初期嘔吐も出ない。胎便は24時間以内に出てしまい重症黄疸もでない。厚労省の「授乳と離乳の支援ガイド」は赤ちゃんを冷え症に陥れ、チアノーゼ(低酸素血症)、低血糖、重症黄疸を増やすことから、「百害あって一利なし」である。赤ちゃんに黄疸が出るのは当たり前の様に考えられているが、重症黄疸は冷えによる便秘と完全母乳による飢餓(脱水+栄養不足)が原因である。生命の安全を考えた時、出生直後のカンガルーケアに何のメリットもない。日本周産期・新生児学会は、生命の安全を脅かすカンガルーケア(早期母子接触)をなぜ中止させないか、疑問である。学会は厚労省を守るのではなく、赤ちゃんを守る本来の姿に戻るべきである。赤ちゃんを守らない学会は解散し、権威のある本来の学会にもどすべきである。 6.「温めるケア」を世界の赤ちゃんに! 久保田産婦人科麻酔科医院では1983年の開業以来、未熟児はもちろん元気に生まれた正常成熟新生児約14.000人の全ての赤ちゃんを出生直後に温かい保育器内(34℃⇒30℃)に2時間収容し、冷え症(末梢血管収縮)を防いできた。保育器内ではもちろん、2時間経って保育器から新生児室のコットに出しても、下肢(足底部)の深部体温が34℃以下になることはない。しかし、体温管理(保温)を怠り、25℃前後の分娩室で管理すると、下肢の体温は生後1~2時間で30℃以下まで低下する。保温を怠ると、冷え症(末梢血管収縮)の危険な状態が継続し適応障害を作り出すのである。末梢血管収縮(放熱抑制)は体温調節には有利に働くが、末梢血管を収縮させるためのホルモン(カテコラミン↑)が呼吸循環動態・肝機能(糖代謝)・消化管機能に悪栄養を及ぼしているのである。つまり、赤ちゃんを元気に育てるためには、出生直後の冷え症を防止し、赤ちゃんを恒温状態により早く安定させることが重要である。日本の分娩室(約 25℃)では、温めるケアが新生児の基本的管理である。しかし、厚労省が勧める出生直後のカンガルーケア(早期母子接触)は、赤ちゃんを冷やすケアである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
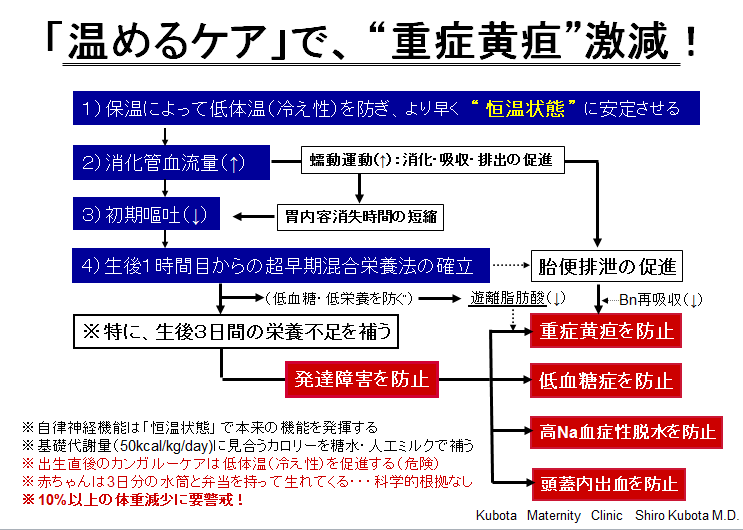 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 久保田史郎 平成25年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温めるケアで“重症黄疸”激減! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
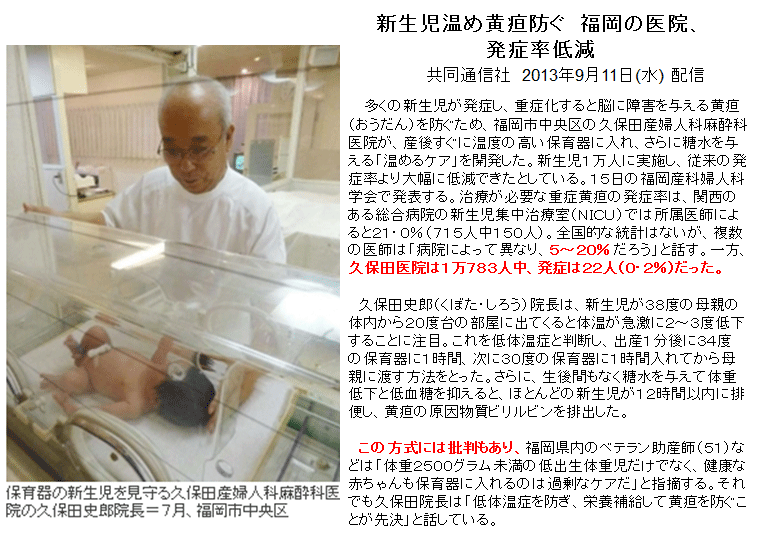 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★続きはこちらから |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当院が出生直後のカンガルーケアをしない理由 出生直後の「温める」ケア |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当院では出生直後の赤ちゃんを保育器内(34℃⇒30℃)に2時間収容します。理由は、温かい子宮内(38℃)から生れてきた赤ちゃんの身体を、分娩室の寒い環境温度(約25℃)に徐々に馴染ませるためです。プール・海水浴で冷たい水中に突然
飛び込むと危険と子供の時に教えられたのと同様に、温かい環境から寒い環境に徐々に慣らす必要があります。特に、出生直後の赤ちゃんは急激な環境温度の低下に遭遇すると、呼吸循環動態に異常をきたし、呼吸障害を引き起こすからです。 日本の分娩室は大人に快適ですが、赤ちゃんには寒すぎです。胎内と胎外の環境温度差、つまり寒冷刺激が強すぎると、児は末梢血管を収縮し放熱を防ごうとします。この時、血管収縮ホルモン(エピネフリン)が分泌されますが、このエピネフリンが手足の血管だけでなく、肺動脈を収縮させ、児に最も危険な肺高血圧症(チアノーゼ)を来たします。出生直後の赤ちゃんのチアノーゼ(低酸素血症)が出るのは生理的ではなく、寒冷刺激が強すぎるためです。34℃の保育器内に収容すると呼吸循環動態は安定しチアノーゼは出ません。 当院が34℃の保育器内に赤ちゃんを収容する目的は、寒冷刺激を少なくし、胎内から胎外生活への適応障害を防ぐ為です。適応障害とは、肺高血圧症(低酸素血症)・低血糖症・重症黄疸などです。これらは発達障害の危険因子として昔から指摘されています。寒い分娩室での出生直後のカンガルーケア(早期母子接触)は赤ちゃんを「冷やす」ケアです。赤ちゃんに優しい病院にカンガルーケア中の心肺停止事故が集中するのは、寒冷刺激が強すぎるにも関らず体温管理(保温)を怠っているからです。うつ伏せ寝での早期母子接触は絶対に止めるべきです。窒息の危険性が高い上に、児の全身状態の観察が全く出来ないからです。カンガルーケアの危険性については、平成24年6月14日、厚生労働省雇用均等・児童家庭局に出向き報告済みです。厚労省は少子化対策の前に、赤ちゃんの脳障害を防ぐために「授乳と離乳の支援ガイド」の見直しを急ぐべきです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成25年9月29日 久保田史郎 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カンガルーケア中の心肺停止事故 SIDS/ALTEは、“隠れミノ” カンガルーケア(早期母子接触)に体温上昇作用はなし 産科医療補償制度原因分析委員会の問題点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カンガルーケア(早期母子接触)中の事故は「親の責任か」? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特集 NETIBニュース カンガルーケア裁判判決(大阪) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生直後のカンガルーケア(早期母子接触)に 終止符! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
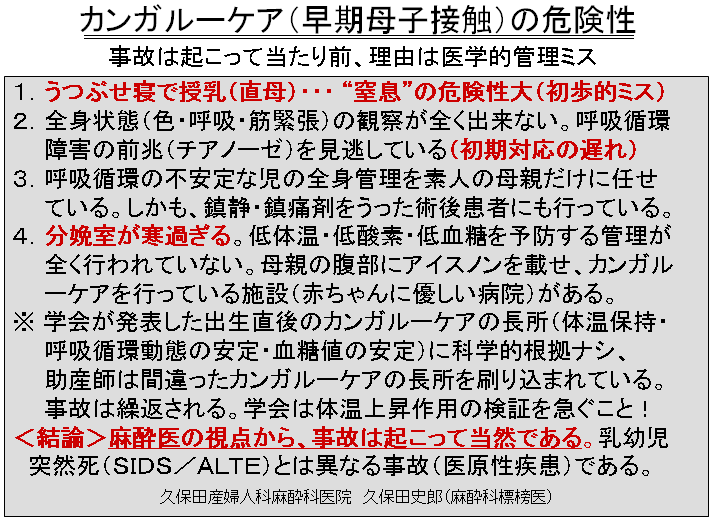 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
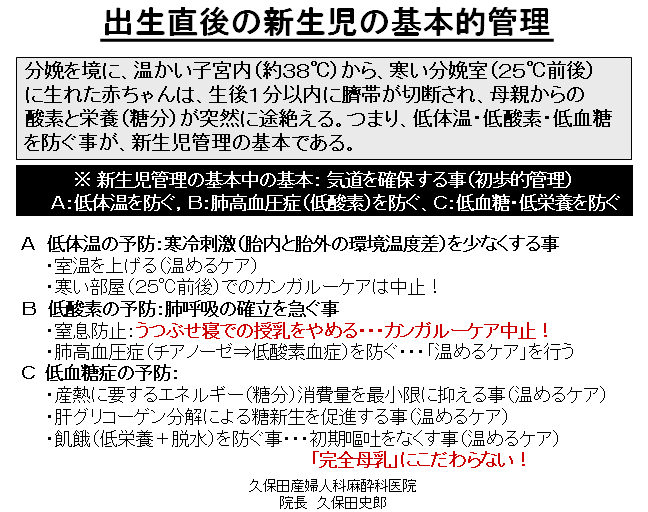 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. うつぶせ寝の危険性・・・気道閉鎖(窒息)を引き起こす 出生直後のカンガルーケア(早期母子接触)は母親の体位が分娩台・ベッド上で水平位のため、お腹の上に乗せられた赤ちゃんは「うつぶせ寝」の状態となる(下図)。児頭の重さ(体重の約1/3)で口腔・鼻腔は塞がれ、解剖学的に気道閉鎖(窒息)を引き起こす危険性がある。乳首は口の中で、赤ちゃんは口呼吸が出来ない上に、頭の重さで鼻腔は乳房に埋もれ、口・鼻呼吸も出来ない状態(気道閉鎖)になる。事故例の多くが、異常発見時に、うつぶせ寝の赤ちゃんの口の中に乳首が入ったままの状態で見つかっている。うつぶせ寝での授乳(直母)は、呼吸管理の上で “初歩的ミス” である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 全身状態の観察が全く出来ない 国(厚労省)は、生後間もない赤ちゃんは呼吸循環動態が不安定と報告している様に、医療従事者は呼吸循環障害(肺高血圧症⇒チアノーゼ)の発生と予防に細心の注意を払う義務がある。しかし、寒い分娩室でのカンガルーケア中に、保温のためのタオル・毛布などで赤ちゃんを被い全身状態を見えなくする保育法は、児を観察する上で致命的となる。呼吸循環障害の指標となる全身色(チアノーゼの有・無)や呼吸障害(多呼吸・陥没呼吸・呻唸・無呼吸など)の前兆を見逃し、初期治療が遅れ、一命は採り止めても脳に障害を遺すからである。同様に、手足の動き(筋緊張度)を観察する事は、低血糖症の有・無を知る上で重要な観察項目である。手足の動きが観察できないことは、低血糖症を見逃すことになる。保温のためにタオル・毛布などで赤ちゃんを被い、全身状態を見えなくするカンガルーケア(STS)は、呼吸循環動態が不安定な時期には絶対に行うべきでない。カンガルーケア中に酸素飽和度をモニターする学会の方針だけでは不十分であり、児の全身状態を肉眼で観察する方法と併用しなければ安全とは云えない。酸素飽和度の低下は呼吸循環障害(窒息・肺高血圧症・低血糖症)の結果であり、それらの異状に対する初期対応が遅れる。全身状態を観察する利点は、呼吸の動き、チアノーゼの有無、手足の動きが一目で分かるからである。呼吸循環障害を酸素飽和度モニターだけに頼る学会の指導は危険が多すぎる。 保育器内で全身状態を観察する利点(動画) 3. 児の全身管理を母親だけに任せている 出生後の呼吸循環動態が不安定な最も危険な時期に、素人の母親だけに児の全身管理をまかせるカンガルーケアは危険極まりない医療行為である。呼吸循環動態が不安定な時期であるからこそ、未熟児管理と同様の濃厚な呼吸循環動態の観察と体温管理・栄養管理を行うべきである。たとえ母親が出生直後のカンガルーケアを強く希望したとしても、体温が恒温状態に安定するまでは行わせてはならない。 帝王切開術後の母親、しかも睡眠をとるべき深夜時間帯にカンガルーケアを行っている施設がある。鎮静・鎮痛剤をうたれた術後患者は、カンガルーケア中に、いつ寝込んでも不思議ではない。睡眠中の母親に児の全身管理、とくに気道確保が出来る訳がない。事故(窒息)は起こって当たり前である。医療従事者(助産師)に母親の術後合併症を防ぐための医学的な基礎知識があれば、カンガルーケアを深夜に行わせることなど無いはずである。睡眠を十分にとらせる事が術後患者の基本的管理である事を知るべきである。 4.日本の分娩室は赤ちゃんに寒過ぎる ■分娩時の寒冷刺激が肺高血圧症(チアノーゼ)を誘発する。 分娩時の寒冷刺激(胎内と胎外の環境温度差)が強すぎると、新生児は生後1時間以内に約2℃~3℃体温が低下する。寒い分娩室(25℃前後)では、赤ちゃんは放熱を防ぐ為に、全身(とくに手足)の末梢血管を持続的に収縮させ体温調節を行う。放熱抑制のための末梢血管収縮にはカテコラミン(血管収縮ホルモン)が分泌されるが、カテコラミンは手足の血管だけでなく、肺血管も同時に収縮する。全ての血管の動き(収縮・拡張)は、環境温度の変化(低温/高温)に対応して、恒温状態を保つための自律神経系(交感・副交感神経)によって支配されているからである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
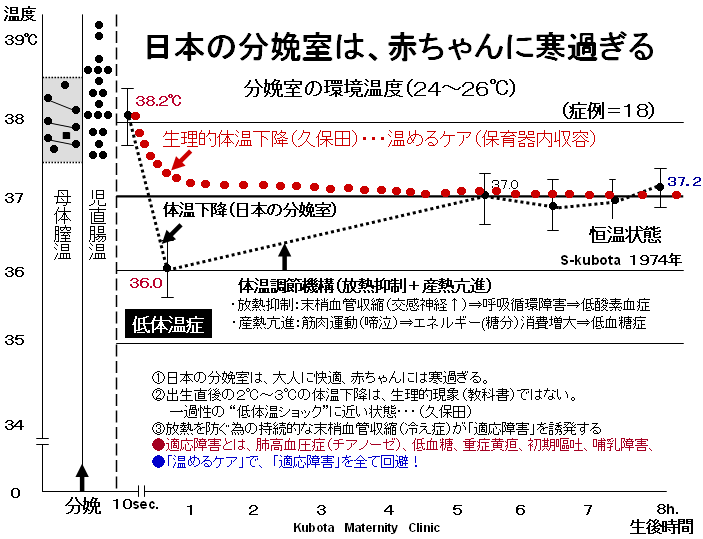 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
つまり、恒温動物である人間の自律神経機能は呼吸循環の安定(肺呼吸の確立)よりも、恒温状態を維持するための体温調節機構(放熱抑制=末梢血管収縮)を優先する。手足の長時間の末梢血管収縮は体温調節に有利に働くが、新生児の呼吸循環の安定には不利益となる。生後間もない赤ちゃんの呼吸循環障害(肺高血圧症)を防ぐ秘訣は、出生直後の新生児に未熟児と同様の快適な環境温度(中性環境温度)を準備することが最も重要である。体温管理(保温)を無視した分娩室・母子同室での長時間のカンガルーケアは「冷やすケア」であり、呼吸循環動態が不安定となり、チアノーゼが出て低酸素血症に陥るのは当前である。 ① 肺高血圧症(チアノーゼ⇒心肺停止)のメカニズム 分娩時の寒冷刺激が強すぎると、手足の末梢血管のみならず肺動脈も収縮し、肺血管抵抗が増す。その結果、心臓(右心室)から駆出された静脈血は肺動脈への流入が妨げられるため、心臓から出た一部の静脈血は肺をバイパスし、血管抵抗の低い胎児期の動脈管・卵円孔を通り大動脈に流入する。新生児にチアノーゼが出る原因は、静脈血が肺でガス交換(酸素化)されないまま大動脈に直接入り込むからである。寒い部屋で長時間のカンガルーケアを行い、体温管理(保温)を怠ると、新生児にとって最も危険な肺高血圧症(チアノーゼ=低酸素血症)の病態が完成する。(肺高血圧症(チアノーゼ⇒心肺停止)のメカニズム図表) 肺高血圧症(心肺停止)を防ぐには、出生直後の室温を中性環境温度(30℃~34℃)に保ち、持続的な末梢血管収縮つまりカテコラミン分泌を抑える為の医学的管理(保育器内収容)が必要である。出生直後の赤ちゃんを生後2時間だけ保育器内(中性環境温度)に収容すると、先天性心臓病の一部を除けば、チアノーゼは出ない。呼吸循環動態の安定(肺呼吸の確立)には、出生直後の「温めるケア」が不可欠である。ところが、寒い分娩室における現行の出生直後のカンガルーケアは「冷やすケア」であり、カンガルーケア中にチアノーゼが出るのは、医療側が新生児の体温管理(保温)を怠った為である。つまり、心肺停止事故は原因不明ではなく、医原性疾患である。 「温めるケア」保育器内収容の図表 ②出生直後のカンガルーケアは、「温めるケア」ではなく「冷やすケア」! 赤ちゃんの呼吸循環動態が不安定な理由は、手足が冷たく、体温が「恒温状態」に安定していないからである。体温が37℃前後の正常域であったとしても、手足が冷たい場合は、カテコラミン分泌亢進のため肺動脈血管は収縮し、肺高血圧症はいつでも起こり得る。生後間もない赤ちゃんの呼吸循環動態が不安定になる理由は、赤ちゃんの冷え性(末梢血管収縮=カテコラミン↑)を見逃し、体温管理(保温)を怠っているからである。 驚くことに、母親の腹部にアイスノンを載せカンガルーケアを行っている事例(赤ちゃんに優しい病院)がある。助産師は冷え性(持続的な末梢血管収縮)の危険性を全く解かっていない。分娩室でのカンガルーケアを推進する新生児科医は、出生直後は体調が急変しやすく、ケアの有無にかかわらず事故が発生すると言い訳するが、急変するのは部屋の温度が寒過ぎるにもかかわらず体温管理を怠っているからである。 事故は、赤ちゃんや母親側に責任があるのでなく、赤ちゃんの体温を管理する医療側に問題(管理ミス)がある。モニターを使い肺高血圧症(チアノーゼ)の早期発見も大事であるが、肺高血圧症に陥らないように医学的管理(温めるケア)をする事が何より重要である。母乳育児の3点セット(カンガルーケア+完全母乳+母子同室)を中止しない限り、カンガルーケア中の心肺停止事故・発達障害の増加に歯止めは掛からない。昔の産婆は、産湯で「温めるケア」をしていたのである。 5.カンガルーケア(早期母子接触)の “体温上昇作用” に科学的根拠ナシ カンガルーケア・ガイドラインワーキンググループは、出生直後のカンガルーケア(STS)には、⑴体温上昇作用、⑵血糖値の安定、⑶呼吸循環の安定などの利点があると報告した。グループの一人渡部医師(倉敷中央病院小児科)は外国論文(ザンビア)を引用し、カンガルーケアの体温保持作用について、「児の体温は保育器に収容するよりもカンガルーケアの方がより早く上昇し安定化する」を日本周産期・新生児医学界誌(第47巻、第4号2011年)に発表した。日本産婦人科医会も同論文(Christensson 1998)を引用し、同様の内容を第50回記者懇談会 (2012年1月18日)で発表した。下図は両学会が引用したChristensson の資料である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
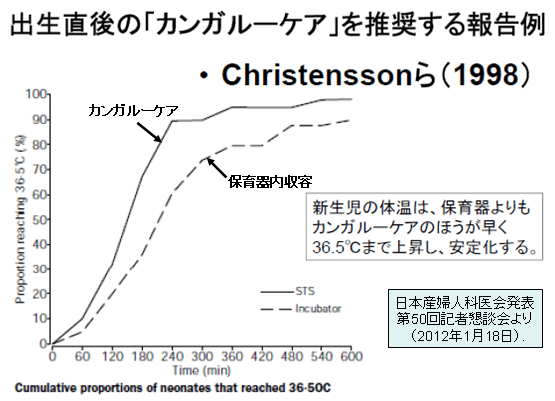 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この論文はNICU入院児(低出生体重児)を対象とした研究であり、分娩時に寒冷刺激を受けた出生直後のカンガルーケア(早期母子接触)の研究結果ではない。両学会は、日本の分娩室において、出生直後のカンガルーケアにChristensson の成績と同様の体温上昇作用があるかどうかを検証すべきである。もし、出生直後のカンガルーケアに体温上昇作用が認められなければ、日本の寒い分娩室でのカンガルーケアは赤ちゃんに優しい「温めるケア」ではなく、赤ちゃんに不利益な「冷やすケア」となり、肺高血圧症(チアノーゼ⇒低酸素血症⇒心肺停止)、低血糖症(発達障害)、重症黄疸(発達障害)の赤ちゃんを増やすことになる。 低血糖症の図表 重症黄疸の原因と予防 ■ 赤ちゃんは、学会が発表したカンガルーケアの長所(体温保持作用)の犠牲に! 日本周産期・新生児医学会と日本産婦人科医会は、赤ちゃんが低体温症や手足が冷たくなった時は保育器に入れて治療するよりも、カンガルーケア(STS)で母親の体温で温めた方がより早く正常体温(恒温状態)に安定する。つまり、両学会は低体温症の赤ちゃんは保育器に入れる今迄の医療よりも、カンガルーケア(STS)で温めた方がより良い結果が出ると、医療現場に混乱を招く内容を発表した。 医学的常識を覆す両学会の発表は、医療従事者(特に助産師)がカンガルーケアの体温上昇作用を信じ、冷たくなった赤ちゃんを保育器ではなくカンガルーケア(STS)を選択する事態が起こり得る。事実、新生児室で生後10時間目の赤ちゃんの手足が冷たくなり、冷たくなった赤ちゃんを助産師が母親の所に連れてきて、「手足が冷たいから抱っこして温めてください」、と言い残して助産師は部屋を出ていき、その後の観察もなかった。児は1時間後に心肺停止状態で見つかった。児は、一命は取り留めたが、現在、脳性麻痺の状態で、意識が無いまま人工的に呼吸管理されている。赤ちゃんに優しい病院(BFH)に認定された病院での出来事である。 ■カンガルーケア(早期母子接触)に “体温上昇作用” は無い! カンガルーケアの長所、⑴体温上昇作用、⑵血糖値の安定、⑶呼吸循環の安定を覆す論文が国内にある。坂口(信州大學医学部)らは、全国産科780施設へのアンケート結果に基づく STS(Early skin to skin contact)の現状と課題、を周産期シンポジウム2010年(No.28)に報告した。 以下、坂口論文を引用:STS導入後に児の状態が悪化したなどの理由でSTSを中断した経験があるかどうかについて検討した、中断したと回答した施設は40%以上にも達していた。STS中断の理由は、チアノーゼの増強、児が冷たくなってきた、酸素飽和度が上昇しない、呼吸をしていない、児の鼻腔圧迫による気道の閉鎖、児が動かなくなった、引用終り。 両学会が発表したカンガルーケアの体温上昇作用が真実ならば、児が冷たくなる事はない。坂口論文のSTS中断の理由は、まさしく肺高血圧症の病態そのものであり、カンガルーケアに体温上昇作用はない事を暗に訴えているのである。(坂口論文のSTS中断の理由の図表) ■ザンビア(後発開発途上国)の臨床データの問題点 学会が引用した体温上昇に関する外国論文は、分娩時に寒冷刺激を受けた出生直後のカンガルーケア(早期母子接触)のデータではなく、NICU入院児のザンビア(南アフリカ)のデータを引用しての報告である。しかも、調査研究の対象は、正常成熟児の早期母子接触のデータではなく、主に早産児(平均33週~34週)、低出生体重児(平均1890g~2183g)であり、入院時の児の平均体温(直腸温)は34℃であったと記録されている。 日本(先進国)の周産期医療の臨床現場に、後発開発途上国(ザンビア)における早産児、低出生体重児の臨床データをなぜ参考文献として引用したのか、両学会の発表は疑問だらけである。このザンビアの論文は、出生直後のカンガルーケア(早期母子接触)の体温上昇説を裏付ける資料として引用するのは不適切である。両学会は、カンガルーケアの体温上昇作用説の検証が終るまで、出生直後のカンガルーケア(早期母子接触)は中止すべきである。学会はカンガルーケアから早期母子接触に名称を変更したが、名称変更で事故が減る筈が無い。正常成熟児で元気に生れても、出生直後の体温管理(保温)を怠り、うつぶせ寝にしてカンガルーケアを行えば、窒息事故・心肺停止事故は必ず起こり得る。事実、名称変更後にも事故は繰返されているのである。 ■国(厚労省)は、分娩直後のカンガルーケアの危険性を知っていた ■カンガルーケア中の心肺停止事故は、厚労省に責任か? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
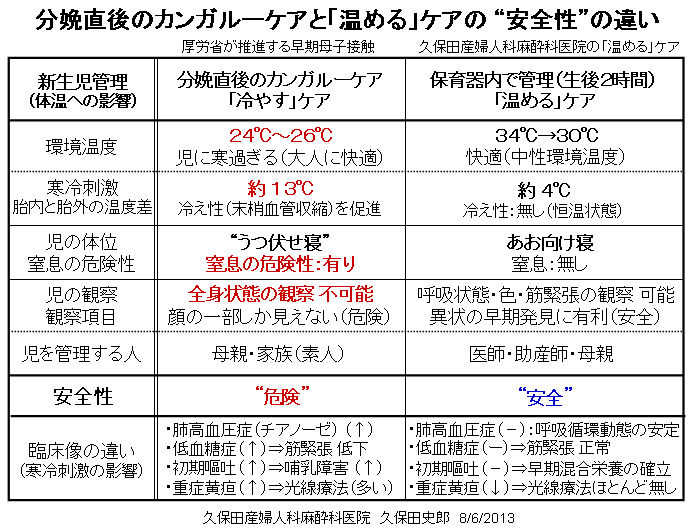 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■発達障害を防ぐ当院の新生児管理法(保温+超早期混合栄養法) 温めるケアを動画で紹介 1.保育器の中で糖水を飲む赤ちゃん(生後1時間目) 2.保育器で恒温状態に落ち着いた赤ちゃん 3.母乳を飲む赤ちゃん 完全母乳で体重減少 4.人工ミルクを飲む赤ちゃん |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成25年8月4日 久保田史郎 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 早期母子接触(分娩室)とカンガルーケア(NICU)との違い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
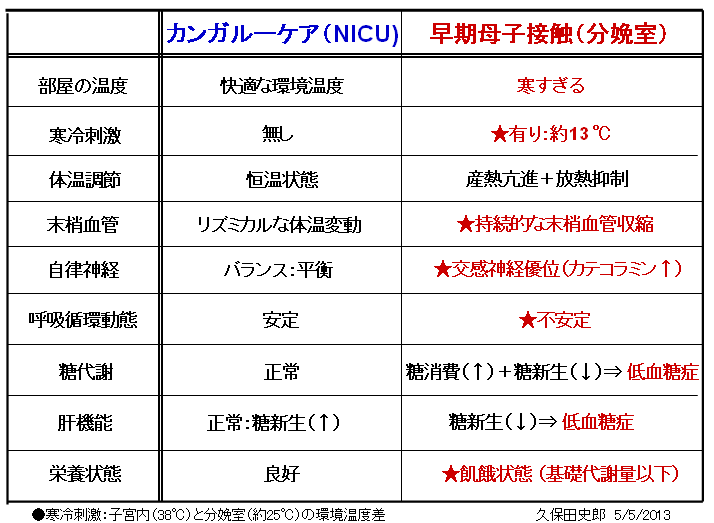 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完全母乳とカンガルーケアは発達障害児の危険因子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カンガルーケア と呼ばないで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カンガルーケア被害者家族の会が厚労省,学会に要請 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厚労省の「授乳と離乳の支援ガイド」に警鐘! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012年5月21日 日本の分娩室は“寒すぎる” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カンガルーケア事故、「患者・家族の会」発足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ カンガルーケア事故 患者家族の会(東京) 「患者.家族の会」発足と決意表明 2011年11月26日 カンガルーケア事故 “助産師中心医療の危うさ” 指摘 被害者の会設立、「国にも責任」 Medical tribune記事 2011年11月29日 カンガルーケア事故 「心肺停止」 のメカニズム 患者家族の会で発表(久保田) 2011年11月26日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カンガルーケアに関する情報(外部リンク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m3.com臨床賛否両論 「産直後カンガルーケアの是非」 久保田史郎の掲載記事全文 出産直後のカンガルーケア中に医療事故に遭われた母親の手記 がんばれ こうたろう 母の苦悩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||